ブラックハットSEOとは?やり方・手法一覧と有効性について

ブラックハットSEOとは、Googleの検索アルゴリズムの裏をかくことで不正に評価を上げさせようとするSEO対策の手法のことです。この記事ではブラックハットSEOがどのようなものか、歴史も含め解説していきます。知らず知らずの内にブラックハットSEOをやってしまいペナルティの対象にならないようにしっかり理解しましょう。
ブラックハットSEOとは?
不正に検索上位表示を目指す手法のこと
ブラックハットSEOとは、検索エンジンのガイドラインに違反する手法を使って、検索エンジンの結果において上位に表示されるようにするSEOのことを指します。 例えば、「有料リンクの購入」や「隠しテキスト」を使い自サイトの評価を高めるなどが該当します。
過去には、Googleのガイドラインに反する施策をしても一定の効果を得られていましたが、アルゴリズムの精度が上がってきた近年では、「検索順位が下がる」「Googleペナルティを受け検索結果に表示されなくなる」など、非常にリスクの高い手法となりました。
ブラックハットSEOの施策内容を理解していないと、意図せずブラックハットSEOをおこなってしまい、それまでに獲得してきたサイトへの評価が台無しになってしまう可能性があります。
ブラックハットSEOのリスクとペナルティの内容
ブラックハットSEOをおこない、Googleからペナルティを受けるとページはもちろん、サイト全体の評価が下がる可能性があります。
▼ 具体的なペナルティの内容としては
- 検索順位が大幅に下落する
- 検索エンジンからインデックスが削除される
- ドメインがインデックスから削除される
- WEBサイトを運営するためのIPアドレスが禁止される
などが挙げられます。
ペナルティの対象になった場合、上位に表示されていたページが100位以下に下落することもあります。
また、ペナルティを受けた場合、サーチコンソールから再審査リクエストをすることで解除の申請をおこなうことができますが、
- ペナルティの解除に時間がかかる
- 場合によってはペナルティが解除されない
- ペナルティが解除されても元の順位に戻らない
などペナルティ以前の状態に戻るのに大きな労力と時間がかかります。
最悪、いちからドメインを取得し直して、サイト運営を始めなければいけなくなるため、Googleのガイドラインに違反するブラックハットSEOの施策には注意しましょう。
ブラックハットSEOの一覧と具体的な手法について
ブラックハットSEOの手法は色々とあるため、代表的な施策内容と各手法について具体的に説明します。
【ブラックハットSEOの一覧】
- 被リンクを大量に設置する
- 隠しリンク
- 隠しテキスト
- リンクファーム
- コメントスパム
- コピーコンテンツ
- 自動生成されたコンテンツ
- ワードサラダで作成したコンテンツ
- クローキング
- 悪意のある動作を伴うページの作成
- サブドメイン貸し・サブディレクトリ貸し
上記で紹介した手法はアルゴリズムの進化によって検索エンジンに見抜かれるため、効果を発揮することはありません。
ただし、意図せずおこなってしまう場合もあるため、次の項目で具体的に説明します。
被リンクを大量に設置する
Googleのアルゴリズムは検索順位を決める際に、対象サイトがどのくらいのリンクを獲得しているのかを、判断基準の1つとしています。
以前は、「リンクが集まっているサイトは他者から評価されている」という基準のもと、検索順位を決めていたため、リンク自体が低品質でもリンクの数が多ければ検索結果で上位表示されていました。
このことから、被リンクを販売する業者が存在している時期もありましたが、「ペンギンアップデート」や「パンダアップデート」以降、低品質な被リンクを大量に獲得する手法はGoogleに淘汰されました。
そのため、現在は自然に獲得した「ナチュラルリンク」や「ドメインパワーの高い関連性のあるサイトからのリンク」しか評価されないようになりました。
現在も、「クラウドワークス」「ココナラ」等の外部委託サービスや、一部のSEO会社が有料リンクの販売をおこなっているのを目にしますが、被リンクの購入や大量にリンクを設置する行為は、ペナルティの対象となるため注意しましょう。
隠しリンク
隠しリンクとは、ページ内にリンクを設置しているにもかかわらずCSSを使って偽装したり、htmlの設定をおこなうことで、ユーザーにはリンクを見せず、クローラーにだけリンクを読み込ませる手法です。
隠しリンクの具体的な設置方法としては、
- 背景と同じ色でリンクを設定する
- フォントサイズを極小にする
- 「, 」や「。」などの1文字にリンクを設定する
などが挙げられます。
このように隠しリンクはサイトを訪問したユーザーに気付かれない様、対象ページへの内部リンクを増やすことで、ページの重要性をGoogleに誤認させることが主な目的です。
しかし、ユーザーにとってメリットがなく、クローラーに読み込ませるだけのリンクと判断された場合には、ペナルティの対象となるため「隠しリンク」を設置する施策はとらないようにしましょう。
隠しテキスト
隠しテキストは、自身のブログや記事内に目には見えないキーワードをたくさん記述し、Googleの検索エンジンに読み込ませ検索順位を上げるという手法です。
意図的にテキストを背景画面の配色と同じに設定したり、文字フォントのサイズを0や1にして記入するなど、画面上ではユーザーにその内容が見えないようにします。
昔は、トピックに関するキーワードが多く利用されている方が検索エンジンからの価値が高く、検索順位が上がりやすいと言われていました。このことから、認識されるキーワードを中心に、隠しテキストを利用して意図的に文字数を増やしていました。
上記のような手法を用いると、ユーザーの目に映るコンテンツとクローラーが認識するコンテンツに乖離が生まれ、検索エンジンから信頼性の低いサイトだと認識されてしまうため、自身のサイトに隠しテキストがあった場合は早急に削除しましょう。
リンクファーム
リンクファームとは、検索エンジンのランキングを上げる目的で、コンテンツの関連性の有無にかかわらず大量の相互リンクをおこなったり、相互リンク目的で作成されたサイト郡のことです。
相互リンク自体がペナルティの対象になることはありませんが、検索順位を操作する目的で過剰に相互リンクをおこなったり、リンクファームに登録することはガイドライン違反となります。
以前はリンクの質よりもリンクの量が重視されていたため、多くのSEO業者が取り入れていた手法でしたが、ペンギンアップデート以降は低品質なリンクを評価しなくなったので現在ではSEO効果もなくなりました。
自身のサイトに相互リンク目的のページが無いか?リンクファームに登録されていないか確認しましょう。
コメントスパム
コメントスパム(スパムコメント)とは、自身とは全く関係のないブログや掲示板にサイトコメント欄から自社サイトに向けてリンクを貼ることで被リンクを獲得する手法です。
コメントスパムをおこなうための自動ツールを導入することで、短時間でコストをかけずに被リンクを獲得することが出来たため、リンクファームと同様に、被リンクの質より量が重視されていた時代に多く見られました。
コメントスパムは、ブログが普及するとともに増えてきました。ブログサイトの運営者側も対策を取り「rel="nofollow"」という属性を付けて、リンクを設置してもリンクジュースが流れなくなるように対応したため、コメントスパムをおこなってもSEO効果は無くなりました。
コピーコンテンツ
コピーコンテンツとは、他サイトのコンテンツをそのまま使用したり、少しだけ修正を加えたコンテンツを使用したりすることを指します。
コピーコンテンツは検索エンジンのガイドラインに違反するため、使用することは避けるべきです。検索エンジンは、重複したコンテンツを持つサイトを低く評価するため、検索結果において上位に表示されにくくなります。
SEO対策に取り組むうえで、「定期的にページを更新したりページ数を増やしたりすることが重要だ」という誤った思い込みをしてしまうと、自身のリソースだけでは独自性にあふれたコンテンツを作成することが出来ず、評判の良いサイトからコンテンツを流用してしまいがちです。
たとえ流用元のコンテンツがどれだけ優れていたとしても、無断で複製されたコンテンツはユーザーにとって価値が無いばかりか、場合によっては著作権の侵害に当たってしまい、訴訟や賠償責任を負うリスクもあるため注意しましょう。
自動生成されたコンテンツ
「自動生成されたコンテンツ」とは、ソフトなどを用いてコンテンツを自動生成することで、コンテンツを量産することを指します。
2023年現在では、ChatGPTなどAIを使ってコンテンツを生成する事も出来ますが、内容によっては不自然な文脈になってしまったり、日本語としておかしな表現が発生することが多く、ユーザーに有意義なコンテンツとして認識されるにはもう少し時間が必要です。
AIを使って自動生成されたコンテンツであっても、ユーザーにとって価値の高いコンテンツであればぺナルティの対象にはならないとGoogleは公言しています。
しかし、自動生成された価値の低いコンテンツと検索エンジンに判断された場合は、ペナルティを課されるリスクがあるため、自動生成されたコンテンツをサイトに載せるのは控えた方が良いでしょう。
ワードサラダで作成したコンテンツ
「ワードサラダ」とは、文法は正しいが意味が支離滅裂になっている文章を指します。
ワードサラダ作成ツールを使って、キーワードに関連する共起語や関連語句を含んだテキストを自動で作成し、被リンクのテキストとして利用することで関連性の高いサイトからの被リンクとして偽装する手法です。
昔の検索エンジンは、日本語の意味まで理解することが出来なかったため、「ワードサラダ」によるブラックハットSEOが流行しました。
現在では、検索エンジンの大幅なアップデートがおこなわれたことをきっかけに、文法だけではなく文章の意味まで正しく理解できるようになり通用しなくなりました。
クローキング
あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、クローキングというブラックハットSEOの手法もあります。
Googleはクローキングを下記の様に定義しています。
検索ランキングを操作したりユーザーに誤解を与えたりすることを目的に、ユーザーと検索エンジンに異なるコンテンツを表示することです。クローキングの例としては、次のようなものが挙げられます。
Google検索セントラル
・検索エンジンには旅行の目的地に関するページを表示しながら、ユーザーに対しては薬の割引に関するページを表示する
・ページをリクエストしたユーザーエージェントが人間のユーザーではなく検索エンジンである場合にのみ、ページにテキストやキーワードを挿入する
つまり、サイトを訪問したユーザーとクローラーに異なったHTMLの内容を表示するということです。
クローラーが訪問してきた時のみ、対策キーワードを大量に詰め込んだHTMLを認識させ、そのページが対象のキーワードに対して情報量が多いかのように誤認させます。検索ユーザーとクローラーとで認識するコンテンツが全く違うものになるので、ブラックハットSEOに分類されます。
クローキングはブラックハットSEOの手法としては通用しなくなってきましたが、画像などGoogleの認識が苦手とするもので構成されているページの場合、知らないうちにクローキングにあたる設定をしてしまうこともあります。
そのため、クローラーとユーザーに見せるページが同一か、サーチコンソールの「URL検査」のレンダリング機能を使って確認しましょう。
悪意のある動作を伴うページの作成
ユーザーの予想や希望とは異なる動きをWebサイト上でするコンテンツは、「Googleから悪意のある動作をするページ」と認識されます。
具体的な動作として、下記のようなものがGoogle検索セントラルで挙げられています。
・ページ上のコンテンツの位置を変更または操作することで、ユーザーが特定のリンクやボタンをクリックしていると認識していても、実際にはページの別の部分をクリックしたことになるようにすること
Google検索セントラル
・ページに新しい広告やポップアップを挿入する、ページ上の既存の広告を別のものに置き換える、またはそのような動作をするソフトウェアを宣伝またはインストールすること
・ユーザーがダウンロードをリクエストしたときに意図しないファイルもダウンロード対象に含めること
・ユーザーのパソコンにマルウェア、トロイの木馬、スパイウェア、広告、ウイルスをインストールすること
・ユーザーに知らせて同意を得ることなくユーザーのブラウザのホームページや検索設定を変えること
ユーザーが求めているもの以外を表示させたり、ソフトフェアの配布、ユーザーの同意なくファイルをダウンロードさせる動きはガイドライン違反の対象となります。
検索クエリに関連したコンテンツを用意し、Web上でのユーザーの安全性を担保したサイトを作るようにしましょう。
サブドメイン貸し・サブディレクトリ貸し
2021年頃から、SEO界隈で話題になっている「サブドメイン貸し」という手法があります。「ホスト貸し」とも言います。公式サイトの下層ディレクトリを、アフィリエイトサイトとして第三者に提供するという手法です。
一般的に大規模サイトや、長期間運営されているサイトはドメイン評価、いわゆるE-A-T(権威性・網羅性・信頼性)が高いので、そのようなサイトのディレクトやサブドメインにあるページをGoogleは信頼性のあるコンテンツとして評価されやすくなります。
また、医院は専門家のサイトとして認識されるため「医療系」などYMYLに関連する業種でも同様にGoogleからの評価を得られます。
このようなアルゴリズムを利用して、アフィリエイト収益を得ている事業者は大手サイトや医療系のサイトを「間借り」し、得られた報酬の一部を対価として大手サイト側に払うという仕組みが生まれ、「サブドメイン貸し」「サブディレクトリ貸し」という手法が急速に広まりました。
このような手法自体、実はGoogleは禁止していませんが、2022年12月から開始した「ヘルプフルコンテンツアップデート」と「リンクスパムアップデート」で順位が大幅に下落したサイトが確認されています。
Googleのガイドラインには明確にスパムとは明記されていませんが、アルゴリズムのアップデートには引っかかっているサイトがあるため、サブディレクトを借りるのも貸すのも注意が必要です。
ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違い
さて、ここまでブラックハットSEOとはどのようなものか、具体的な手法を含め解説してきました。
本項では、ブラックハットSEOとは真逆にあたるホワイトハットSEOとの違いを解説します。
Googleガイドラインに則っているか
ブラックハットSEOと、ホワイトハットSEOの一番大きな違いは「Googleが推奨するガイドラインに則っているか」という点です。
ブラックハットSEOはGoogleの検索アルゴリズムの裏をかき、不当に評価を得て検索順位を上げようとする施策です。
一方、ホワイトハットSEOはGoogleが評価するサイトとはどのようなものか、正しく理解したうえで対策をする、いわゆる正攻法の施策となります。
ホワイトハットSEOに取り組む際に、参考にするべきコンテンツは、本項の最後でも紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。
ユーザーファーストになっているか
検索エンジンに対してだけでなく、検索ユーザーに向けたサイト構成やコンテンツ内容になっているかも、ホワイトハットSEOとブラックハットSEOの大きな違いです。
ブラックハットSEOは、ユーザーのためにはなり得ない不正なリダイレクト設定やコンテンツ位置の操作など、ユーザーを欺くような行為です。
ホワイトハットSEOは、ユーザーにとって有意義なコンテンツの作成や、サイト巡回のしやすさ、適切な内部リンクなど、サイト訪問者の利便性を追及してすすめていく取り組みになります。
サイトを運営していくうえでのターゲットが、ブラックハットSEOとホワイトハットSEOでは違うのです。
ブラックハットSEOは今でも有効なのか
結論から言うと、ブラックハットSEOは今では通用しなくなってきています。
ブラックハットSEOをおこない、上位に表示されるサイトは、ユーザーにとって有益なものとは言えない場合が多く、Googleとしても臨むところではありません。
検索ニーズに応えられる適切な検索結果にするために、Googleはアルゴリズムのアップデートをおこなってきました。
技術の進歩に伴い、ブラックハットSEOはアルゴリズムで検知され検索結果には表示されないようになっていますが、アップデートがおこなわれるたびに、不正な対策を用いてランキングを操作しようとするサイト運営者やSEO業者が存在するのも事実です。
仮に検索順位が上がったとしても、定期的におこなわれるGoogleアップデートで昨日まで通用していたブラックハットSEOが、今日には通用しなくなることもあり得るため、Googleのガイドラインに反したブラックハットSEOは、取り組むだけ時間の無駄と言えるでしょう。
ブラックハットSEOをおこなっているサイトを報告する方法
ブラックハットSEOを行っている可能性があるサイトを見つけた場合、Googleに報告することが出来ます。
▼ 報告する先は以下になります。
【Googleの報告ページ】
Search Console – ウェブスパムが見つかりましたか?
【Google有料リンクの報告ページ】
https://www.google.com/webmasters/tools/paidlinks
【bingの報告ページ】
https://www.microsoft.com/ja-jp/concern/bing
「Google検索セントラル」から「スパム、有料リンク、マルウェア」として報告することで、アルゴリズムのスパム検出の精度を上げることに活用されるので、もしブラックハットSEOが疑われるサイトを見つけたら報告しましょう。
ブラックハットSEOの歴史と衰退の背景
先述している通り、横行するブラックハットSEOに対応すべくGoogleはアルゴリズムのアップデートを繰り返してきました。
ここではブラックハットSEOがどのように横行し、淘汰されてきたか解説していきます。
アルゴリズム技術の進化
2000年に登場したGoogleの検索エンジンは、当時、いくつか存在した検索エンジンの中で初めて被リンクによって、Webサイトを評価するアルゴリズムを取り入れた画期的な検索エンジンでした。
しかし、2000年~2012年頃まではブラックハットSEOでランキングを操作することが、簡単にできるアルゴリズムでした。
対策として、Googleはリリース時の2000年から、数多くのアップデートをおこなってきましたが、2011年~2012年にかけてリリースされた2つのアルゴリズム「パンダアップデート」と「ペンギンアップデート」によって低品質なコンテンツの見極めや、悪質なリンクファームなどを高精度で見極められるように進化しました。
そのため、数多く存在したブラックハットSEOの手法のほとんどが通用しなくなり、検索結果からも排除できるようになりました。
ではGoogleが開発した画期的なアルゴリズムである「パンダアップデート」と「ペンギンアップデート」について簡単に説明していきます。
パンダアップデート
パンダアップデートとは、2011年にリリースされたWebサイトのコンテンツ品質を評価するためのアップデートです。
以前はGoogleから公式にアナウンスされ、定期的に更新がされてきていましたが、Googleのコアアルゴリズムに組み込まれ、現在ではデフォルトで存在するアルゴリズムになっているため、アナウンスはありません。
このことから、Googleがコンテンツ品質をどれほど重要視しているかが分かると思います。
パンダアップデートがリリースされることで、無断複製されたコピーコンテンツや自動生成されたコンテンツは評価されないようになり、低品質なコンテンツが掲載されたサイトは大きく順位を落とすことになったのです。
ペンギンアップデート
ペンギンアップデートは、2012年にリリースされた被リンクの品質を評価するアップデートです。
現在では、ペンギンアップデートもパンダアップデートと同様にGoogleコアアルゴリズムに組み込まれ、Googleの検索アルゴリズムになくてはならないアルゴリズムの1つです。
このアップデートで、リンクプログラムへの参加やリンクの購入、人工的な被リンクの作成、隠しテキスト、クローキングをおこなっているサイトが順位下落の対象となりました。
ブラックハットSEO業者の代名詞とも言える、被リンクの大量設置が取り締まりの対象となったため、ブラックハットSEOの衰退に一躍を担い、現在の健全な検索結果に多大なる貢献をしたアルゴリズムと言えるでしょう。
ブラックハットSEOにならないために読むべきコンテンツ
ここまでブラックハットSEOについて解説してきましたが、ブラックハットSEOに該当するか否か、判断基準は常に見直されていますし、新たなブラックハットSEOも残念ながら生まれ続けています。
「自覚せずにブラックハットSEOをしてしまっていた」というようなことを回避するためには、定期的に最新情報を収集する必要があります。
情報収集する際に役立つメディアなどをご紹介するので、是非参考にしてみてください。
検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド
Googleが検索セントラルで公開している、「オンラインコンテンツを所有または管理されていて、Google検索を通じた収益化や宣伝を強化したいとお考えの方」を対象とした、SEOの基礎知識を包括的に学べるガイドブックです。
コンテンツをクローリングしてもらいやすくする方法や、インデックス登録についてなどSEO対策に取り掛かるうえで不可欠な情報が多くなっています。
Google公式 SEOスターターガイド | Google 検索セントラル
Google検索の基本事項(旧Webマスター向けガイドライン)
以前は 「Webマスター向けガイドライン」と呼ばれていましたが、2022年10月に名称変更され「Google検索の基本事項」になりました。
- 技術要件
- スパムに関するポリシー
- 主なベストプラクティス
についてまとめられています。
Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)| Google 検索セントラル
Google検索品質評価ガイドライン
「General Guidelines」という題目で英語版のみ提供されている、検索結果の品質を評価するためのガイドラインです。
- 検索需要との一致について
- ページ品質について
- ユーザービリティ(サイトの使いやすさ)
などについて解説されています。ただし、日本語版のリリースはされていません。
アイレップ株式会社などが独自に日本語に翻訳して公開しているので、色々と探してみると良いかもしれません。
まとめ
ブラックハットSEOについて、以前横行していた手法や衰退の歴史、ここ数年で広まりつつある新たな手法について解説してきました。
冒頭でも触れたように、ブラックハットSEOがどのようなものなのか、しっかり理解しておかないと、自分でも気付かない内にペナルティの対象になりかねません。本項目を参考に健全にSEO対策を取り組んでいきましょう。
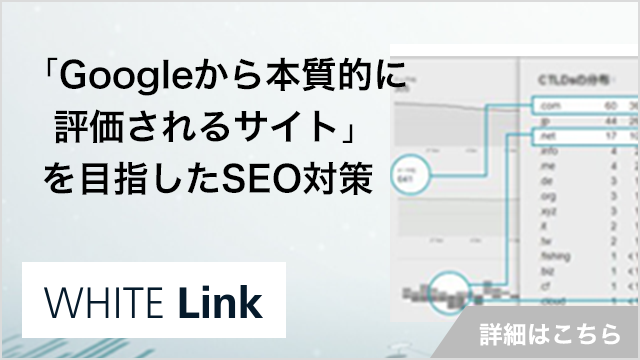
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














