メタディスクリプションとは?SEO効果・書き方・例文・文字数を解説

SEO対策をしていると、メタディスクリプションという単語を目にする機会が多いと思います。「メタディスクリプションはどこに表示されるのか」「なぜ設定する必要があるのか」「どうやって設定するのか」気になっている方も多いのではないでしょうか?本記事では、メタディスクリプションの概要から目的、SEO効果などについて解説します。
メタディスクリプション(meta description)とは
メタディスクリプション(meta description)は、検索結果にWEBページを要約した説明文を表示するためのHTMLタグです。メタディスクリプションを設定する事で、ユーザーは検索結果からページの内容を理解しクリックするかどうかを判断する事が出来ます。
メタディスクリプションタグを設定すると、検索結果画面の「URL」「ページタイトル」の下に説明文として表示されます。(下記画像の赤枠部分)

表示されたテキストの中に、検索キーワードと同一のキーワードが入っている場合は、キーワードが太字で強調されて表示されます。
メタディスクリプションを設定するメリット
メタディスクリプションを設定する一番のメリットは、検索画面上のクリック率の向上です。ユーザーは検索結果から、自分のニーズや質問に最も適した回答を提供するページを探します。
競合サイトに比べてユーザーの関心を引く魅力的なメタディスクリプションを設定する事で、ユーザーのクリック率を向上させます。
上記以外にもページの目的にマッチしたユーザーからのアクセスを増やす事が出来たり、検索エンジンがぺージの内容を理解しやすくなるといったメリットがあります。
検索結果からのクリック率が向上する
前述した通り、魅力的なメタディスクリプションは、検索結果でのWEBサイトのクリック率を向上させる重要な役割を果たします。
ユーザーは、タイトルタグとメタディスクリプションを基にクリックを決定します。例えば、「3分で作れる栄養満点の朝食レシピ」のような魅力的な説明はクリック率を高めます。
一方で、このページにメタディスクリプションがない場合、検索エンジンはページの内容から無作為にテキストを抜き出して表示することになります。この場合、表示されるテキストがユーザーにとって魅力的でないか、あるいは関連性が低い可能性があります。その結果、ユーザーは他のWEBサイトをクリックするかもしれません。
つまり、魅力的で関連性の高いメタディスクリプションを設定することは、WEBサイトの訪問者数を増やす事に大きく貢献します。
ページの目的にマッチしたユーザーからのアクセスが増える
メタディスクリプションを設定するもう一つのメリットは、ページの目的にマッチしたユーザーからのアクセスが増えることです。例として、あるWEBサイトが「初心者向けのガーデニングのヒント」に関するページを持っているとしましょう。
このページのメタディスクリプションに「初心者でも簡単に始められるガーデニングの基本やコツを紹介します」と記載されていれば、ガーデニング初心者が検索結果を見たとき、このページが自分のニーズに合っていると感じる可能性が高くなります。
結果として、このページには初心者を対象とした内容を求めるユーザーが集まりやすくなります。
また、ページの目的とユーザーの目的がマッチしている場合は、記事の滞在時間が伸びる可能性があります。その結果、別のページの遷移やサイトのブックマークなども期待できます。
メタディスクリプションのSEO効果
メタディスクリプションのSEO効果について正しく理解する事で、最適なSEO戦略を行う事が出来ます。
この項目では、メタディスクリプションがSEOにどのように影響するのかを解説します。
メタディスクリプションに直接的なSEO効果はない
メタディスクリプションを設定しても、しなくてもSEOに直接効果はありません。Googleは、検索セントラルブログの中でメタディスクリプションタグをランキングで使用しないと明言しています。
ただし、魅力的なメタディスクリプションを設定する事で、検索結果でのクリック率が高まるなど間接的なSEOの効果が期待出来ます。実際に検索セントラルブログを確認すると2009年の投稿で以下のように記載がありますが、SEO対策を行う目的は順位を上げる事ではなく、ぺージの流入数やコンバージョンを増やす事です。
ページの内容をユーザーに正確に伝えるために設定された魅力的なディスクリプションは、間接的なSEO効果があると言えます。
表示するスニペットに description meta タグを使用する場合でも、Google のランキングでは description meta タグは使用されません。
Google はウェブ ランキングにキーワード メタタグを使用しません
検索エンジンがぺージの内容を理解しやすくなる
前述したように、メタディスクリプションにはSEOへの直接的な影響はありませんが、ページの内容を理解しやすくする役割を持っています。具体的にはページごとに独自のメタディスクリプションを設定する事で、GoogleにWEBサイト内の各ページの内容を正しく理解してもらう事ができます。
理由は、Googleはテキスト情報からだけではなく、meta情報からもページの内容を理解しているため、metaタグのひとつであるメタディスクリプションタグで記述されたテキストも参考にしているためです。検索エンジンからページの内容を正しく理解してもらう事で、ユーザーが検索したキーワードと関連するページと判断される可能性が高まります。
その結果、ターゲットキーワードで検索結果に表示されやすくなるという事です。
メタディスクリプションの最適な文字数は70~85文字
メタディスクリプションタグに設定した文章は検索結果に表示される際にGoogleによって文字数の制限を受けます。
検索結果にはPCデバイス・スマホデバイス共に70文字~85文字表示され、それを超えた分の文章はGoogle側の判断で途中で切り詰められて表示されません。
そのため、メタディスクリプションタグに設定する文字数は70文字~85文字以内で作成するようにしましょう。
【70文字〜85文字以内の場合】

【85文字以上の場合】

▼ 実際に、検索結果にメタディスクリプションが何文字表示されるか調査した結果は以下になります。
・調査日:2023年11月21日
・調査デバイス:スマートフォン
・調査キーワード: マーケティング
【調査結果】
| 順位 | 表示された文字数 |
|---|---|
| 検索1位 | 79文字 |
| 検索2位 | 82文字 |
| 検索3位 | 80文字 |
| 検索4位 | 71文字 |
| 検索5位 | 83文字 |
デスクトップで検索した場合でも、スマートフォンと同じ文字数が表示されました。
上記調査結果から、2023年11月時点ではメタディスクリプションの最適な文字数は70文字〜85文字となります。
メタディスクリプションの書き方とポイント
▼ 魅力的なメタディスクリプションを書くためには、以下の書き方とポイントを意識する事が重要です。
・フレームワーク「PASBECONA」を意識する
・ページの内容を簡潔に要約する
・クリックしたくなるような内容を記述する
・ターゲットを明確にする
・重要なキーワードは前半に入れる
・ページに関連するキーワードを適度に含める
それぞれ詳しく解説します。
フレームワーク「PASBECONA」を意識する
「PASBECONA」は、神田昌典さんが提唱した人の心を動かすためのフレームワークです。主にキャッチコピーで利用されますが、メタディスクリプションを作成する場合にも応用する事ができます。
PASBECONAを基本とする事で、魅力的でクリックされやすいメタディスクプションを作成する事が出来るようになるため、是非覚えてみてください。
▼ PASBECONAは、以下9つの項目に沿って文章を書く事でユーザーの購買行動を促す事ができます。
1. Problem(問題)
2. Affinity(共感)
3. Solution(解決策)
4. Benefit(利得)
5. Evidence(証拠)
6. Contents(内容)
7. Offer(提案)
8. Narrow down(絞り込み)
9. Action(行動)
各要素についてそれぞれ解説します。
Problem(問題)
ターゲットオーディエンスが直面している問題や、課題を認識していることを記載する事で、訪問者が自分の状況に関連する情報を提供していると感じることができます。
例えば、メタディスクリプションに「肌の乾燥や敏感肌に悩んでいるあなたに」と記述することで、そのような肌の問題を持つユーザーに直接語りかけます。
Affinity(共感)
ターゲットオーディエンスの感情や、経験に共感する内容を含めると訪問者との関係構築や信頼の醸成に役立ちます。
例えば、「私たちも同じ悩みを経験した元に解説」と書くことで、ユーザーの経験に共感し、関係を築くことができます。
Solution(解決策)
提供している製品やサービスに対して、訪問者の問題を解決できるかを強調します。解決策は明確かつ具体的であるべきです。
例えば、「当社の独自開発の保湿クリームが、あなたの肌をしっとりと潤す」といった具体的な解決策を提示します。
Benefit(利得)
訪問者が提供されている解決策を利用することで得られる具体的な利益を示します。これには、効率の向上、コスト削減、生活の質の向上などが含まれます。
例えば、「導入した事で離職率が改善し、平均継続年数が向上します」と、製品の利用による具体的な利益を強調します。
Evidence(証拠)
証拠や実績は、提案の信頼性を高めるために重要です。例えば、統計データ、専門家の推薦、顧客の証言などが記載します。
例えば、「数千人の顧客からの高評価と、皮膚科医の推奨」といった、製品の信頼性と効果を裏付ける証拠を提示します。
Contents(内容)
ページの主要な内容や特徴を簡潔に説明することで、訪問者がページに何が含まれているかを素早く理解できます。
例えば、「当社の製品は全て天然成分で作られ、敏感肌の方にも安心してご使用いただけます」と、ページの主要な内容や製品の特徴を紹介します。
Offer(提案)
特別なオファーやプロモーションを提示することで、訪問者の興味を引き、クリックスルー率を高めることができます。
例えば、「今だけ限定で初回購入者には20%オフ」といった特別なオファーを提示します。
Narrow down(絞り込み)
特定のターゲットオーディエンスに焦点を当てることで、関連性が高く関心を持ちやすい訪問者を引き付けることができます。
例えば、「初回購入者限定、20%オフになるクーポンを発行中」と特定のターゲットオーディエンスを明確にすることで、関連性の高い訪問者を引き付けます。
Action(行動)
訪問者に何らかの行動を促す言葉を含めることで、実際にページを訪れるよう促します。「詳細を見る」「今すぐ購入」などのフレーズが含まれます。
例えば、「今すぐ詳細を確認して、特別オファーを利用しましょう」という言葉で、訪問者にページへのアクセスや製品の購入を促します。
これらの要素をメタディスクリプションに組み込むことで、訪問者にページを訪れる理由を与え、検索結果ページでの効果を最大化することができます。
ぺージの内容を簡潔に分かりやすく要約する
メタディスクプションはページの内容を簡潔に分かりやすく要約します。伝えたい事を詰め込み過ぎて長くなると、何が言いたいのか分からない説明文になってしまい、ページの内容がユーザーに伝わりません。
また、専門用語を説明文に多用し過ぎると、用語を理解出来ない初心者にページの内容が伝わらないため、クリックされない可能性が高くなります。特定の分野だけで使用されているキーワードの場合でも、キーワード周辺の用語についてすべての検索ユーザーが熟知しているとは限りません。
メタディスクプションは、誰が見ても一目でページの内容が分かるように要約するのがポイントです。
クリックしたくなるような内容を記述する
メタディスクリプションは目にしたユーザーが、思わずクリックしたくなるような内容を書きましょう。
検索ユーザーは、ページのタイトルやスニペットに表示されるテキストから、どのページをクリックするか判断します。自分が知りたい情報が得られないと判断すれば、タイトルリンクがクリックされることはありません。
▼ クリックしたくなるようにするためには、先ほど紹介した「PASEBECONA」だけではなく、以下の項目も意識して作成します。
1. メリットを明確に記述する
2. ベネフィットを記述する
3. 悩みを解決できることを記述する
4. 製品・商品の場合は価格を記載する
検索したユーザーがクリックしたくなるような、魅力的なメタディスクリプションを書くように心掛けましょう。
ターゲットを明確にする
メタディスクリプションを書く際は、ターゲットを明確にすることが重要です。
例えば、「外部リンクについて詳しく知りたい」ユーザーが対象であれば、「外部リンクについてどのようなことが記述されているのか?」「この記事を読むことで外部リンクに関する知識がどの程度得られるのか」を記述する必要があります。
「誰が」「どのような状況で」「どのような悩みを」を意識してディスクリプションを作成することで、説明文の内容とマッチしたユーザーは、「このページを見る事で解決できる」と考えるためクリック率を高めることができます。
重要なキーワードは前半に入れる
ページのテーマを表す重要なキーワードは説明文のメタディスクリプションに入れるようにしましょう。ユーザーによっては、検索結果に表示されるメタディスクリプションを全部読まずに一部だけを見てページの内容を判断する可能性があります。
その際、ページの内容を表すキーワードが説明部の後半にあったら、ページの内容を理解しないままクリックをせずにスルーをしてしまうかもしれません。また、検索結果に説明文のスニペットとして表示される文字数は70文字〜85文字程度なので、長すぎると後半部分が途切れて表示されなくなります。
その為、ページのテーマを表す重要なキーワードを前半部分に入れて検索結果画面を見たユーザーがクリックしてくれるようにしましょう。
ページに関連するキーワードを適度に含める
メタディスクリプションには、ページの内容に関連するキーワードを適度に含める事で、下記が可能です。
・ユーザーにページのテーマを理解してもらう
・検索エンジンにページの内容を正しく伝える
たとえば、「タイトルタグ」に関するページを持っている場合、メタディスクリプションには「タイトルタグ」というキーワードを自然に組み込むことで、ユーザーと検索エンジンに対してもタイトルタグについてのページである事が伝わります。
メタディスクプションの例文
まずは、メタディスクリプションを作成する際の例文を「悪い例」「良い例」それぞれ紹介します。
【✕】 キーワードを羅列しただけの悪い例
検索上位表示やアクセス数アップ、キーワード設定、コンテンツ制作、内部・外部対策など、SEO対策ならなんでもお任せください!
→ どのテーマについて書かれているのか、どのキーワードで上位表示を狙っているのかが分かりにくい。
【✕】 サービス提案・商標ページの悪い例
〇〇〇のことなら△△△にお任せください!
→ ページの要約になっておらず、具体的なサービスの内容や他社との違いも分からない。
【✕】 文字数が少なすぎる悪い例
SEO対策ならお任せ!
→ ページの要約になっておらず、具体的な内容が分からない。
【〇】 良い例
SEO対策の意味と効果、やり方を初心者向けに画像付きで解説。上位表示させるためのノウハウと自分で行うためのチェックポイントをわかりやすく紹介します。
→ 読者の共感が得られる内容が盛り込まれており、具体的な内容も把握できる。
サイトのタイプごとに使える簡単なテンプレートを作成したので是非利用してみてください。
■メディアサイトテンプレート
「【ページの主要な話題やトピック】について徹底解説。【補足情報や特徴的なコンテンツ】に本記事を見れば誰でも簡単に理解する事ができます。【メディア名】では、専門家が最新情報を定期的に発信しています。」
■ サービスサイトテンプレート
「【サービス内容の概要】を提供しています。【補足情報やサービスの特徴】により、【特定のニーズや問題】を解決。【業界名】の事なら実績のある【会社名】にお任せください。」
■ コーポレートサイトテンプレート
「【企業の主要な業務や製品/サービス】に関する詳細情報。【会社名】は【製品/サービス】をおこなっている会社で、【企業の使命、価値観、社会的責任などの補足情報】を提供します。
■ ECサイト商品ページテンプレート
「商品名」なら「会社名」にお任せ。「会社名」は全国どこでも【送料無料】で配送中。安心&安全 人気「商品名」を多数取扱い!今なら【特別オファー】実施中なのでお得に購入可能です。
メタディスクリプション設定時の注意点
▼ メタディスクリプションを設定する際は、必ず以下の注意点を守った上で設定します。
・メタディスクリプションを重複させない
・メタディスクリプションに記号・絵文字を使用しない
・キーワードを乱用しない
これらの注意点を無視した場合、クリック率の低下や間接的なSEO効果の減少に繋がります。
それぞれ詳しく解説します。
メタディスクリプションを重複させない
メタディスクリプションをサイト内で重複させてはいけません。メタディスクリプションに設定する説明文はサイト内で重複させずにページごとに独自の説明文を設定します。
同じ説明文を使い回してしまうと、各ページのテーマが検索エンジンに正確に伝えられず、カニバリゼーションが発生する可能性があるためSEO的にはマイナスとなります。
また、ユーザーが自社サイト内の異なるページを検索結果画面で見た場合、同じページと判断してクリックされない可能性もあります。
▼ よくあるメタディスクリプションが重複している例は、以下になります。
・TOPページとサービス紹介ページのメタディスクリプションが同じ
・特定のブランドに関する商品ページのディスクリプションが全て同じ
メタディスクプションがサイト内で重複しているどうかを確認するには「Ubersuggest」というツールを使う事で簡単に見つける事ができます。
【Ubersuggestで重複したメタディスクプションを見つける手順】
1. Ubersuggestをクリック
2. 「サイト監査」をクリックしてURLを入力
3. 「発見されたSEOの問題」をチェック
複数のページに同じテキストが設定されていると、「発見されたSEOの問題」の中に「メタディスクリプションが重複している」と表示され、さらに「詳細を見る」をクリックすると重複したURLが表示されます。

Ubersuggestについては、別記事で詳しく解説しているので興味がある方は以下ページをご確認ください。
メタディスクリプションに記号・絵文字を使用しない
メタディスクリプションには、記号や絵文字を設定しない事が推奨されています。記号や絵文字はユーザーが使用するデバイスによって表示されないため、意図しない見え方になる可能性があります。
また、Googleのジョン・ミュラー氏は、公式動画の中で「記号や絵文字をスニペットには意図的に表示しない場合もある」とも発言しているため、使わざるを得ない場合を除いては使用しない方が良いでしょう。
【参考動画】
ただし、「SEO対策として使用しても問題はなく、検索順位が低下したりペナルティを受けたりすることはない」とも述べているため、何らかの理由で記号や絵文字を使わざる終えない場合は、利用しても問題ありません。
キーワードを乱用しない
メタディスクリプション内で同じキーワードを乱用してはいけません。キーワードを過度に含めると、不自然な文章や、読みづらい文章になるため、クリック率が低下する可能性があります。
また、過度にキーワードを詰め込むと、検索エンジンから評価を低下させる可能性があります。キーワードを無理に詰め込むのではなく、自然かつ適切な方法でメタディスクリプションに組み込むことが重要です。
キーワードの乱用とは、Google 検索結果のランキングを操作する目的で、ウェブページにキーワードや数字を詰め込むことです。キーワードの乱用では、不自然にリストやグループの形式を使ったり、関連性のない場所でキーワードが記載されたりする傾向があります。
Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー:キーワードの乱用
メタディスクリプションの設定方法
メタディスクリプションの設定方法は、HTMLに記述する方法とCMSの管理画面で設定する方法と複数あります。
本記事では、HTMLに直接記述する方法とWordpressで設定する方法を紹介します。
メタディスクリプションをHTMLに記述する方法
HTMLでメタディスクリプションを設定するには、HTMLファイルの「head」セクションにメタタグを追加します。
<meta> タグは、「name」属性に「description」を指定し、「content」属性にページの要約を入れます。
▼ 実際に記述すると以下のようになります。
<head>
<meta name=”description” content=”ここにページの要約を入れます” />
</head>
設定する際の注意点としてメタディスクリプションタグは、必ずHTMLソースの<head>内に記載します。

WordPressでメタディスクリプションを設定する方法
WordPressで作成されたサイトの場合は、使用するテーマによっては投稿画面の下部もしくは右側の指定された箇所にテキストを入力するだけで設定できます。
対応していないテーマの場合は、プラグインを導入することで入力欄が表示されます。
【メタディスクリプションが設定できるテーマの例】
・JIN
・Diver
・SANGO
・AFFINGER5
・Cocoon
【メタディスクリプションが設定できるプラグイン】
・Yoast SEO
・All in one SEO Pack
「All in one SEO Pack」をインストール・有効化すると投稿画面の下に、「All in one SEO pack」というスペースが新たに追加され、「説明」の右側の空欄にテキストを入力することで設定が完了します。
メタディスクリプションが設定できるテーマに、上記プラグインがインストールされていると、テーマ側とプラグイン側の両方で入力欄が表示されてしまいます。両方に設定しないように注意しましょう。
メタディスクリプションの確認方法
メタディスクリプションは、WEBページのソースコードを直接見ることで確認する事ができます。まず、確認したいWEBページをブラウザで開きます。次に、ブラウザ上で右クリックして「ページのソースを表示」を選択します。
キーボードショートカットを使う場合は、Windowsでは「Ctrl + U」、Macでは「Command + Option + U」を使用します。
ソースコードが表示されたら、メタディスクリプションを探します。検索機能(ブラウザでは通常「Ctrl + F」)を使って「<meta name="description"」と入力することで、該当部分を簡単に見つけることができます。
上記方法以外にも、ツールを使うと簡単に確認する事が出来ます。
それぞれ解説します。
ツールで確認する方法
メタディスクプションは、Google chromeのプラグインなどサードパーティツールを使って確認する事が出来ます。
▼ メタディスクリプションを確認する事が出来るプラグインは、以下になります。
・見出し(hタグ)抽出:ラッコツールズ
・SEO META in 1 CLIC
・Web ToolBox
プラグインをインストール後、確認したいページを表示してプラグインのアイコンをクリックすると設定したメタディスクリプションが表示されます。

全ページのメタディスクリプションを一覧で確認する方法
「Screaming Frog SEO Spider」を導入している場合は、サイト内の全ページのメタディスクリプションを一覧で確認する事が出来ます。無料でも利用できますが、無料版の場合は確認できるURLは500件までとなります。
【Screaming Frogを使って全ぺージのメタディスクリプションを一覧で確認する手順】
1. 「Screaming Frog SEO Spider」をインストール
2. サイトのURLを入力
3. 「Start」をクリック
4. タブからmeta descriptionを選択すると一覧が表示されます。

メタディスクリプションに関するよくある質問
メタディスクリプションが検索結果に反映されるまでどのくらいの時間がかかりますか?
Googleのクローラーがメタディスクリプションを設定してページをクロール後に、検索結果に反映されるためサイトによって異なります。
すぐにクロールして欲しい場合は、GoogleサーチコンソールのURL検査ツールからリクエストを送りましょう。
設定したメタディスクリプションが検索結果に反映されません。
設定後に、Googleのクローラーがページをクロールしたかどうかを確認します。
クロール済みにも関わらず検索結果に反映されていない場合は、メタディスクリプションの設定ミスや設置場所にミスが無いかどうか?ページの内容を表す適切な内容になっているかを確認しましょう。
まとめ
今回は、メタディスクリプションの概要から目的、SEO効果などについて解説しました。サイト運営者が作成したテキストを、Googleにスニペットに表示して欲しいと伝えるタグがメタディスクリプションです。
どのようなテキストでも必ず表示されるわけではなく、設定しても適切な内容でなければ検索結果には表示されない場合があるため、設定方法や書き方のポイント、設定時の注意点を確認した上で適切な設定をおこない、表示されているかを実際に検索して確認しましょう。
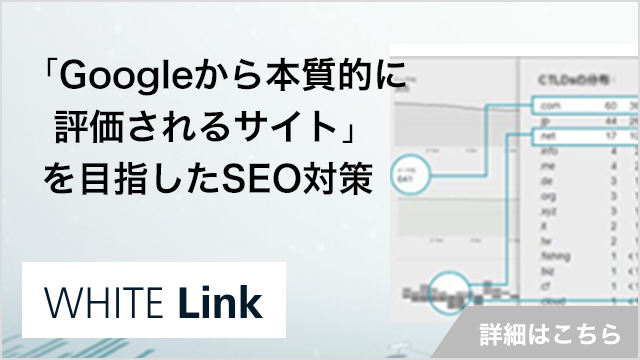
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














