パンダアップデートとは?由来と実施状況・SEOへの影響を解説

パンダアップデートとは、2011年に行われたGoogle検索エンジンのアルゴリズムアップデートのひとつです。低品質なコンテンツを検索結果から排除し、良質なコンテンツを検索結果に表示することを目的として導入されました。本記事では、パンダアップデートの概要から導入された背景、対象となるサイト、対策ポイントまで解説します。
パンダアップデートとは
パンダアップデートとは、2011年に米国のGoogleで導入されたGoogle検索エンジンのアルゴリズムアップデートです。
アップデートの内容は、低品質なコンテンツを検索結果から排除し、良質なコンテンツを検索結果に表示することを目的として導入されました。
日本では2012年に導入され、その後も定期的にアップデートを繰り返し、最後に確認されたパンダアップデートは、2015年7月18日に導入されたパンダアップデート4.2です。
パンダアップデートという名称には、Googleのアルゴリズム開発に大きく関わったNavneet Panda氏(ビスワナス・パンダ氏)が由来になっている説と、サイトの評価を白黒させるという意味が込められている説があります。
以下は、2012年7月18日水曜日に、Google検索セントラルブログに投稿されたパンダアップデートについてのGoogleの説明になります。
Google はこれまで 良質なサイトをユーザーに届けること に力を注いできました。その一環として、2011 年には、通称"Panda アップデート"と呼ばれる アルゴリズムの変更を 英語 や その他多くの言語 において実施しています。この"Panda アップデート"はこれまで日本語や韓国語など一部の言語では実施されていませんでしたが、本日 Google は、日本語、韓国語でも実施したことをお知らせします。
引用元:Google 検索が、高品質なサイトをよりよく評価するようになりました
このアルゴリズムの変更では、低品質なサイトの掲載順位を下げ、同時に、良質なサイトの掲載順位をより適切に評価します。例えば、ユーザーにとってあまり価値のないサイト、利便性の低いサイト、他のサイトからのコピーで構成されているようなサイトの掲載順位は下がります。一方、独自の研究や報告、分析など、ユーザーにとって重要な情報を提供しているサイトの掲載順位はより適切に評価されるようになります。この変更は、日本語、韓国語ともに約 4% の検索結果に影響する見込みです。
パンダアップデートの導入背景
Googleがパンダアップデートを導入した意図は、低品質なコンテンツを検索結果から排除し、良質なコンテンツを検索結果に表示することにあります。
パンダアップデートが導入される前の2010年頃は、アフィリエイトリンクをクリックさせる目的のコンテンツや、検索上位表示をさせることのみを目的としたWEBサイトが検索結果の上位を独占していました。
一方で、ユーザーにより役立つ良質なコンテンツを持つWEBサイトが、低品質なコンテンツに埋もれてしまい、検索結果で上位表示されないという状況が続いていました。
Googleは、良質なコンテンツが埋もれてしまう状況は、ユーザーの利益にならないと考え、低品質なコンテンツを検索結果から排除し、良質なコンテンツを検索結果に表示するために、パンダアップデートを導入した訳です。
パンダアップデートとはGoogleアルゴリズムの1つ
パンダアップデートとは数百あると言われているGoogleのアルゴリズムの一つです。パンダアップデートはペナルティと考えているサイト運営者も多くいますが、ペナルティではなく、WEBサイト全体の品質を評価するアルゴリズムの一つに過ぎません。
Googleは、パンダアップデートについて以下のように検索セントラルブログで解説しています。
パブリッシャーの皆様には、Google の現在のランキング アルゴリズムやシグナルの解釈に注意を払うのではなく、ウェブサイトで最良のユーザー エクスペリエンスを提供することに、引き続き注力することをおすすめします。以前の Panda アルゴリズムの変更を気にかけていた方もおられますが、Panda は今年中に 500 件ほど実施される検索の改善案のひとつにすぎません。事実、Panda を実施してから、ランキング アルゴリズムに数十もの微調整が加えられています。それを知らずに、ランキングの変化が Panda に関連していると勘違いされる向きがあります。検索は複雑で常に発展し続ける科学技術です。特定のアルゴリズムの微調整に注力するのではなく、ユーザーに最良のエクスペリエンスを提供することに注力することをおすすめします。
質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス
また、パンダアップデートはページ単位で低品質なぺージの順位を下げるのではなく、WEBサイトに低品質なコンテンツが多く含まれている場合、低品質なサイトと評価されサイト全体での検索順位を下げるアルゴリズムです。
▼ Googleのジョン・ミューラー氏も、パンダアップデートはサイト品質を考慮していると述べています。
パンダアップデートはGoogleのアルゴリズムの一部であり、Googleのペナルティではないため低品質なコンテンツを削除し、コンテンツの品質を高めることで順位を回復させることができます。
ペンギンアップデートとの違い
「パンダアップデート」が、WEBサイト内のコンテンツの質に対する評価をするためのアルゴリズムであるのに対し、「ペンギンアップデート」は、過剰なリンクによるSEOやブラックハットSEOを行うWEBサイトを排除するためのアルゴリズムです。
どちらのアップデートも、Googleの検索結果の品質を向上することを目的に導入されているため、ユーザーにとって有益な情報を提供するWEBサイトを作り続けることが最も有効な施策となります。
パンダアップデートによるSEOの影響
パンダアップデートによるSEOへの影響は、2011年2月24日の導入時に一番大きな影響があり、英語圏で11.8%の検索結果に影響を与えました。
その後は未発表も含めて28回のパンダアップデートが実行されましたが、バージョンによって影響度が異なります。
初回のパンダアップデート以降は、検索結果に与える影響が1%~2%と影響が少ないように見えますが、初回のアップデートで低品質に該当する殆どのサイトを排除出来た事と、多くのサイト運営者がパンダアップデートへの対策として、低品質なコンテンツを削除したことが理由だと考えられます。
重要なことは「検索結果への影響が少ない=効果が無い」ではなく、SEOへの影響が多いためパンダアップデートの対象となる低品質なコンテンツを作らないということです。
【2011年に実施されたパンダアップデートの検索結果への影響の割合】
| 実施された日時 | 検索結果への影響 |
| 2011年2月24日 | 11.8% |
| 2011年4月11日 | 2% |
| 2011年5月10日~7月23日 | 公表なし |
| 2011年8月12日 | 6-9% |
| 2011年9月28日 | 公表なし |
| 2011年10月19日 | 2% |
| 2011年10月19日 | 1%以下 |
パンダアップデートの対象となるコンテンツ
パンダアップデートで影響を受けるサイト、コンテンツには以下のようなものがあります。
1.無断で複製されたコピーコンテンツ
- 他サイトに書かれている内容をコピーしたコンテンツを掲載している
- 外部サイトのページを無断で複製し、ツールを使用して加筆・修正をおこなったページ
- 外部サイトのページを無断で複製し、語句を置き換えたり、類義語に変換したりしただけのページ
2.価値の低いアフィリエイトサイト
価値の低いアフィリエイトサイトとは、ページ内の情報量が少なく、ユーザーの課題を解決できないコンテンツや、アフィリエイトのみを目的としたコンテンツです。以下のようなコンテンツが該当します。
- ページにアフィリエイトリンクを含んでおり、販売元からコピーしたレビューを使っている
- 独自性のあるコンテンツ内容がなく、サイト全体がアフィリエイトで構成されている
- 広告のバナーがページ内での割合を多く占めているページ
3.自動生成されたコンテンツ
自動生成されたコンテンツとは、コンテンツを自動的に生成するプログラムを使用して作成されたページです。人による編集がされない状態で作られたコンテンツで、文法自体は正しく配置されていますが、実際に読むと支離滅裂な内容の文章になっています。
ただし、「ChatGPT」などのAIが自動生成したコンテンツのように、意味の通じる文章となっている場合は、自動生成されたコンテンツに該当するのか判断が難しい所です。
パンダアップデートの実施状況
パンダアップデートは、2011年2月にはじめて導入され、2015年7月までに、計28回のアップデートを繰り返しています。
実施当初はパンダアップデートを手動で更新していたため、Googleから実施したと発表がありましたが、2013年6月にパンダアップデート自体は継続しておこなうものの、公表はしないとGoogleが発表し、通常のアルゴリズムアップデートとして自動で更新がおこなわれています。
そのため、現在では基本的に告知はされません。
しかし、2014年5月20日に実施されたパンダアップデート4.0、2014年9月25日のパンダアップデート4.1、2015年7月18日のパンダアップデート4.2については告知されており、再度パンダアップデートが実施される可能性がありましたが、2023年現在はアルゴリズムに組み込まれているため、今後パンダアップデートは無いと考えられます。
余談で、公式サイトでの発表ではありませんが、Google検索担当副社長の「Kim Hyung-Jin」は、SMX基調講演でパンダアップデートは「ハナグマ」に代わったと発言しています。
「ハナグマ」も白黒の動物になるため、Googleは白黒の動物名をアップデート名にするのが好きなのかもしれませんね。
【参考ページ】GoogleのPandaアルゴリズムがCoatiアルゴリズムに進化
アップデート情報は、「Google検索セントラルブログ」や「Google Search Central」のTwitterにアップされるため、定期的に確認しておきましょう。
・Google 検索セントラルブログ
・Google Search Central Twitterアカウント
【過去に実施されたパンダアップデートの検索結果への影響の割合】
| バージョン | 実施された日時 | 検索結果への影響 |
| パンダアップデート1.0 | 2011年2月24日 | 11.8% |
| パンダアップデート2.0 | 2011年4月11日 | 2% |
| パンダアップデート2.1 | 2011年5月10日 | 公表なし |
| パンダアップデート2.2 | 2011年6月16日 | 公表なし |
| パンダアップデート2.3 | 2011年7月23日 | 公表なし |
| パンダアップデート2.4 | 2011年8月12日 | 6-9% |
| パンダアップデート2.5 | 2011年9月28日 | 公表なし |
| パンダアップデート3.0 | 2011年10月19日 | 2% |
| パンダアップデート3.1 | 2011年11月18日 | 1%以下 |
| パンダアップデート3.2 | 2012年1月18日 | 公表なし |
| パンダアップデート3.3 | 2012年2月27日 | 公表なし |
| パンダアップデート3.4 | 2012年3月23日 | 約1.6% |
| パンダアップデート3.5 | 2012年4月19日 | 公表なし |
| パンダアップデート3.6 | 2012年4月27日 | 公表なし |
| パンダアップデート3.7 | 2012年6月9日 | 1% |
| パンダアップデート3.8 | 2012年6月25日 | 約1% |
| パンダアップデート3.9 | 2012年7月24日 | 約1% |
| パンダアップデート3.9.1 | 2012年8月20日 | 約1% |
| パンダアップデート3.9.2 | 2012年9月18日 | 0.7%以下 |
| パンダアップデート | 2012年9月27日 | 2.4% |
| パンダアップデート | 2012年11月5日 | 1.1% |
| パンダアップデート | 2012年11月21日 | 0.8% |
| パンダアップデート | 2012年12月21日 | 1.3% |
| パンダアップデート | 2013年1月22日 | 1.2% |
| パンダアップデート | 2013年3月15日 | 公表なし |
| パンダアップデート | 2013年7月18日 | 公表なし |
| パンダアップデート4.0 | 2014年5月20日 | 公表なし |
| パンダアップデート4.1 | 2014年9月25日 | 公表なし |
| パンダアップデート4.2 | 2015年7月18日 | 公表なし |
パンダアップデートへの対応方法
パンダアップデートに対応するうえで重要なことは、低品質なコンテンツの見直しをおこない、ユーザーの役に立つ高品質なコンテンツを作成することです。
Googleは、2011年5月6日にパンダアップデートの対象となったサイト運営者向けに、Google検索セントラルブログ内でガイダンスをリリースしています。
この中には「質の高いサイトとみなされるもの」という項目があり、ページの品質が高いかどうかを判断する上で重要な23個の質問があります。
まずは、自身のサイトにGoogleからの質問を当てはめてみましょう。
以下、Googleからの質問をSEM Plus編集部で要約したものになります。
【質の高いサイトとみなされるもの】SEM Plus編集部要約
- 提供されている情報は、Googleのポリシーや基準に従って精査されているか。
- 情報は、Googleの製品やサービスに精通した社員や専門家によって提供されているか。
- プロジェクト内で、同じトピックや類似のトピックに対してキーワードのバリエーションをわずかに変えただけの重複しているコンテンツが存在しないか。
- ユーザーがクレジットカード情報や個人情報を安心して入力出来るサイトか。
- 提供される情報に誤字・脱字・誤情報がないか。
- 提供される内容は、ユーザーが本当に求める情報か。それとも単にSEOで上位表示を達成するためのものか。
- 独自の技術・情報・レポート・調査・分析などが含まれているか。
- 競合他社と比較して、提供される情報やサービスが優れた価値を持っているか。
- コンテンツの品質管理は十分に行われているか。
- コンテンツは公平に作成されているか。
- WEBサイトは、その分野の専門家として認知されている期間によって運営されているか。
- 外部委託が多い場合、品質が一貫して保たれているか、プロジェクトのアイデンティティが保持されているか。
- 提供されるコンテンツは適切に編集されており、急いで作成された印象を与えるものではないか。
- 健康や医療に関連する情報の場合、その情報が信頼性を持っているか。
- サイト名を見たユーザーが信頼できるソースから提供された情報と認識できるか。
- トピックについての情報は包括的かつ、詳細に記載されているか。
- 単に基本的な情報ではなく、洞察に富んだ分析や新しい情報を提供しているか。
- 自分自身で使いたくなる、または同僚に勧めたくなるような内容のページであるか。
- ページ内の広告が、コンテンツの妨害やユーザーエクスペリエンスを妨げになっていないか。
- ページ内の情報は、雑誌・百科事典・書籍などの印刷物で情報源で引用されるほどの価値があるか。
- コンテンツは十分な長さで、有益な詳細情報が提供されており、情報が不完全でないか。
- 提供されるコンテンツにおいて、高品質な部分と低品質な部分が混在していないか。
- ユーザーがGoogleのサービスや製品を利用する際に、不満や不便を感じることがないように配慮されているか。
参考ページ:質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス
いかがでしたでしょうか?
質問に該当する箇所がある場合は、コンテンツを改善することで順位の下落を防ぐだけでなくランキングの上昇が見込めます。
まとめ
今回は、パンダアップデートが導入された経緯や、ペナルティを受ける可能性が高いサイトの特徴、今後の対策について解説しました。
ユーザーにとって価値の低いコンテンツを作成すると検索順位が低下したり、インデックスから削除されたりする恐れがあります。
常日頃からユーザーにとって品質の高いコンテンツ・ぺージ作成を意識していれば、パンダアップデートだけではなく、Googleのアップデートを心配する必要はありません。本記事で紹介した、パンダアップデートの歴史や対策ポイントを意識し、ユーザーへ価値を提供できるコンテンツを作成しましょう。
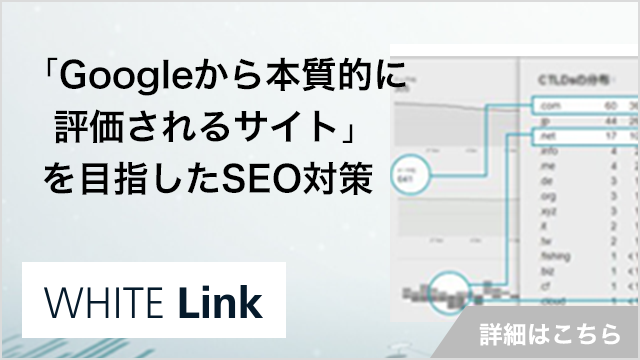
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














