検索順位の仕組みとは?Googleの評価プロセスを解説

本記事ではSEOの土台であるGoogleについて理解を深めるために、Googleが検索順位を決定する仕組みや、決定までのプロセス、ランキングに関連するアルゴリズムについて解説します。Googleがどのようにクロール・インデックス・ランキング決定を行ってているかを理解することで、効果的なSEOの打ち手を考えることができるようになります。
検索順位の仕組み
Google検索は、入力された検索クエリに対し、ユーザーが知りたい情報や問題が解決されるような適切な情報を掲載するWEBページを検索結果に表示させます。
とはいえ、検索クエリに関連がありそうな情報が数百万件も存在した場合、検索結果に表示される情報は一体どのように発見されているのでしょうか。
検索結果に情報を表示するために、Googleは次のような仕組みで動いています。
- クロール
- インデックス登録
- 検索アルゴリズム

クロール
ページの検索順位が決定し、検索結果画面に表示されるためには、GoogleのクローラーがWEBページを発見しクロールしてもらう必要があります。
クロールとは、GoogleのクローラーがWEBページを読み込みテキストや画像・動画などの情報を収集することを指し、ここで収集されたメタ情報やテキスト情報はランキングを決定する際に利用されます。
また、robots.txtのdisallowでクロールをブロックしている場合や、noidexタグを設定している場合は次の行程となるインデックス登録が行われないため、検索結果にページが表示されません。
インデックス登録
インデックス登録とは、クロールしたページの情報をGoogleのデータベースに登録する事を指します。
インデックス登録をする段階で、titleタグやalt属性、テキスト情報、見出しの情報などページ情報にある様々な要素を分析し、既にWEB上にあるページと重複やページの品質などを比較して問題が無ければインデックスに登録します。
一度インデックス登録されたからと言って、永遠に登録されている訳ではありません。クローラーが再度訪問した際に低品質と判断された場合は、インデックス登録から除外されることもあります。
尚、クロールとインデックスが完了して、初めて検索順位が決定するプロセスに進むことが出来ますが、ここまでの工程の中にランキングアルゴリズムは一切関係がありません。
検索順位が決定されるのはこの後の行程となります。
検索アルゴリズム
Googleのランキングシステムは、200以上にも及ぶとされる独自のアルゴリズムで構成されています。これらの検索アルゴリズムは、ユーザーが求めている情報と返すべき情報を様々な要因を基に分析し、順位を決定して検索結果に瞬時に表示しています。
つまり、Googleはユーザーが検索を行った際に、インデックスした様々な情報の中からユーザーにとって最適なページを「ぺージの品質」「ページの信頼性」「ユーザビリティ」「ロケーション」「検索履歴」などをアルゴリズムによって評価し、検索結果に表示しています。
Googleが検索順位を決定するプロセス
【クエリに対する検索順位の決定プロセス】
- 検索キーワードの意味を分析する
- 検索キーワードとの関連性を照合する
- ページの品質・有益性を評価する
- ユーザビリティを評価する
- ユーザーの背景を考慮する
検索順位の決定プロセスは、上記の5段階で表されます。詳細を見ていきましょう。
検索キーワードの意味を分析する
クエリに対し、最適な回答を検索結果に表示させるために、Googleでは検索内容からユーザーの検索意図を推測します。クエリに含まれる単語の意味を分析し、ユーザーがどのような回答を検索結果に求めているか予測します。
▼ Googleは、以下のようなシステムを利用して検索意図を理解しています。
- 自然言語処理(NLP)
Googleは自然言語処理技術を使用して、検索クエリ内の言葉の意味、文脈、文法的な役割を理解します。 - 意図の識別
Googleはクエリを分析して、ユーザーの意図を特定します。これには、情報を求めているのか(情報クエリ)、特定のWEBサイトを探しているのか(ナビゲーショナルクエリ)、あるいはオンラインで商品やサービスを購入したいのか(トランザクショナルクエリ)などがあります。 - クエリの拡張
Googleは、類義語や関連する概念を使用してクエリを拡張したり、より精密な検索結果を提供するためにクエリを調整します。
検索キーワードとの関連性を照合する
次に、クエリにマッチする情報が含まれるWEBページを探し出します。検索アルゴリズムは、そのキーワードの登場頻度やページ上のタイトルや見出し、本文中のテキストなどを分析し、検索インデックス内から適切なWEBページを見つけます。
さらに、検索アルゴリズムは検索キーワードの照合に加えて、クエリに関連する画像や動画などのコンテンツがそのページに含まれているかどうかを分析し、ユーザーが使用する言語にマッチしたWEBページを優先します。
つまり、ユーザーが検索したクエリの意図にマッチしないページはこの時点でランキングから振り落とされます。SEOでは検索意図の理解が最も重要と言われる理由がこれです。
ページの品質・有益性を評価する
検索クエリによっては、関連するWEBページの数が膨大なケースがあります。その為、検索エンジンは検索クエリに対して関連性だけでなく、WEBページの有用性を評価するためのアルゴリズムを作成しています。
その指標の一部が以下です。
- WEBページの新しさ
- 検索キーワードの出現回数
- 情報の信頼性や権威性、専門性
- 著名なWEBサイトからのリンク etc
ユーザビリティを評価する
検索順位を決定する上で、ユーザーにとって使いやすいなども評価するアルゴリズムが含まれています。そのため、他社のコンテンツと比較して品質に大きな差が無い場合は、ユーザーにとって使い勝手が良いページが優先的に表示されます。
ページの表示速度やレイアウトのズレなどを評価するCVWや、モバイルデバイスに特化したページを評価するモバイルフレンドリーなど、ページエクスペリエンスに関連する項目が高いページは優先的に検索結果の上部に表示されます。
ただし、いくらページエクスペリエンスが高くても、ページ自体の品質に問題がある場合は検索結果には表示されません。
ぺージエクスペリエンスに関しては、Googleサーチコンソールのページエクスペリエンスレポートから確認することが出来ます。

ユーザーの背景を考慮する
Googleでは、ユーザーの過去の検索履歴や検索設定などの情報、ユーザーの位置情報などを基にして文脈を考慮します。
例えば、ユーザーが「ラーメン」と検索した際、検索エンジンはユーザーの検索意図はラーメンの歴史や成分を調べているのではなく「近くのラーメン屋を探している」と読み取り、さらにIPアドレスからユーザーの位置情報を読み取り、近隣にあるラーメン屋を検索結果に表示します。
また、よく見ているWEBサイトに関連するキーワードで検索すると、通常よりもそのWEBサイトは上部に表示されるようになります。
検索順位の仕組みに関連するアルゴリズム
検索順位を決定する仕組みの中にはどのようなアルゴリズムがあるのか、一部抜粋してご紹介します。
PageRank
PageRankとは古くからあるアルゴリズムの1つで、第三者のページから自社のページに向けたリンクを「投票」と見なし、リンクを獲得している数や質に基づいて、そのページの重要性を評価する仕組みです。
高いPageRankを持つページからのリンクは、低いPageRankを持つページからのリンクよりも価値が高いと見なされ、高いPageRankを持つページから多くのリンクを獲得することで評価が高まります。
PageRankについては、別ページで詳しく解説しています。
ヘルプフルコンテンツシステム
ヘルプフルコンテンツシステムとは、ユーザーにとって満足度が高いページを評価するアルゴリズムです。
ヘルプフルコンテンツシステムの特徴は、大きく2点です。
- ページ単位ではなく、サイト全体の品質を評価する
低品質なコンテンツの割合が多いサイトの場合はサイト全体で検索順位が下がる可能性がある。 - ペナルティではない
ヘルプフルコンテンツシステムはGoogleによるペナルティではないため、サイト内にある低品質なコンテンツを削除すれば検索順位が戻る(上がる)可能性があります。
レビューシステム
レビューシステムとは、商品やサービスについて質の高いレビューを掲載しているページをより評価するシステムです。
例えば、商品を実際に使ってみた使用感や体験談の掲載、商品に関する調査・分析結果の掲載など、その商品を購入するユーザーにとって価値の高い情報を掲載しているページが評価される仕組みです。また、レビューを行う人物の専門性なども一緒に評価されます。
商品やサービスに関する情報を、公式サイトやインターネット上にあるソースを掲載しただけでは評価の対象にはなりません。
フレッシュネスシステム
検索クエリが鮮度に関係する場合に、最新の情報やユーザーが求めている情報が記載されているページを評価する仕組みです。
Googleの公式ページには以下のように説明されています。
公開されたばかりの映画について検索されたら、おそらくクランクインの時期の記事ではなく最近のレビューを探していると判断します。
フレッシュネスシステム
フレッシュネスシステムは、ニュース・イベント・製品リリース・映画のレビューなど、時期や時間によって検索意図が変化する検索クエリに対して検索結果に表示させるページを変更するアルゴリズムです。
検索順位の仕組みの例外:強調スニペット
強調スニペットとは、検索結果の1位の上部にキーワードに対しての回答を表示する仕組みのことで、キーワードの回答を要約した文章や表が表示されます。

強調スニペットは1位にサイトが必ず表示される訳ではなく、強調スニペットに表示されたページが1位に表示される仕組みです。また、同じキーワードでも強調スニペットが表示される時とされない時があります。
そのため、検索アルゴリズムによって10位前後に表示されているWEBページでも、強調スニペットに選ばれた場合は1位に表示されます。強調スニペットが表示される仕組みは、検索順位を決定する通常の仕組みとは別のプロセスとなるため、例外と言えます。
まとめ
今回はGoogleが検索順位を決定する仕組みやプロセスについて解説しました。
Googleは常にユーザーにとって利用価値が高い検索エンジンであることを目指しているため、SEO対策を行う際もGoogleと同様に、ユーザーにとって利用価値の高いサイトを目指すことで、必然的に検索順位は上がっていきます。
Google検索エンジンをハックするような手法で順位を上げても、一時的な結果になるためGoogleの考えを理解してユーザーファーストなサイトを作りましょう。
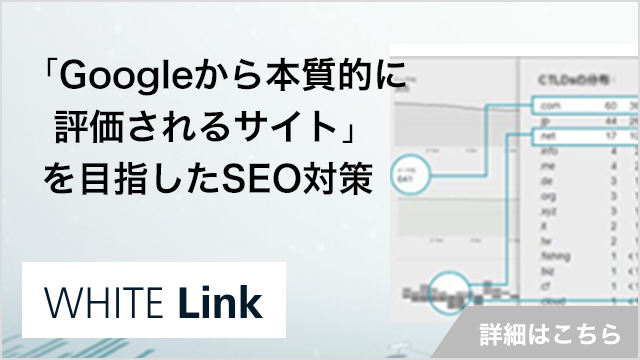
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














