SEOとは?SEO対策の基本と上位表示のポイントを解説

SEO対策について具体的にどのような施策をするのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では、10年間で約3,000社のSEO支援をおこなってきたSEOのプロが、SEO対策を行う上での基本と上位表示させるポイントから、Googleの基本理念と評価の仕組みまで初心者にも分かりやすく解説します。
SEOとは
SEOとは、「Search Engine Optimization」を略したもので、直訳すると、検索エンジン最適化を意味します。読み方はエス・イー・オーです。
SEO対策とは、GoogleやYahoo!・Bingといった主要な検索エンジンでキーワード検索した際に、運営しているWEBサイトやブログをオーガニック検索(自然検索)結果の上部に表示させるための手法を指します。
検索するユーザーの検索意図にマッチしたコンテンツやページを作成することで、Googleアルゴリズムによってページが評価され、検索結果の上部に表示されます。
WEBサイトが上位表示されるとユーザーからの流入数が増加するため、集客数の増加・認知度の増加・コンバージョン数の増加が期待できます。
SEOは検索エンジンごとに施策をおこなう必要がありますが、検索エンジンのなかでもGoogleは世界のシェア率が9割を超えており、検索エンジンというとGoogleを思い浮かべる人がほとんどでしょう。
Yahoo!もGoogleの検索アルゴリズムを採用しているため、実質的にSEOというとGoogleの検索エンジンに対して取り組むことが一般的です。
【検索】ユーザーが質問の回答や製品・サービスを探す際におこなう行動
【検索エンジン】ユーザーが検索をおこなうためのWEBサイト
【検索エンジン最適化】ユーザーが検索エンジンを使って検索をした際に、自サイトを検索結果に表示させるための手法
SEOとSEMの違い
SEMとはSearch Engine Marketing(検索エンジンマーケティング)の略で、検索エンジンを対象にしたマーケティング戦略を指します。具体的には「オーガニック検索からの集客を目的としたSEO」と、「有料広告枠からの集客を目的としたリスティング広告」両方からのアクセスや集客、認知度を向上させる戦略の総称です。

ただし、最近ではエリアに関連するキーワードで検索した際に、検索結果に表示されるローカルパックからの集客を目的としたMEOも含んで定義される場合があります。
- SEO:オーガニック検索からの集客を増加させる手法
- SEM:オーガニック検索と有料広告枠からの集客を増加させる手法
となり、SEOはSEMに含まれる一部の手法となります。
SEMとは半分がSEO、もう半分がリスティング広告と覚えておきましょう。
次の項目では、簡単にSEOとリスティング広告の違いについて説明します。
SEOとリスティング広告の違い
リスティング広告とは、検索結果に表示される有料の広告枠のことです。クリックが発生するたびに費用が発生します。広告主は、検索結果に表示させたいキーワードに対して入札をおこない、広告がクリックされた場合にのみ入札した金額が広告費としてかかります。
また、リスティング広告は設定をしたらその日のうちに検索結果に表示されるため、即効性を求めている場合や、掲載したい期間が限定されている場合に有効なマーケティング手法です。
▼ SEO対策とリスティング広告を比較すると以下のような特徴があります。
| 費用 | 掲載までの時間 | クリック率 | CVR | ターゲット層 | |
| SEO | 無料 | 時間がかかる | 高い | 高い | 潜在層・顕在層 |
| リスティング広告 | 有料 | 即日 | 低い | 低い | 顕在層向け |
SEOとリスティング広告はどちらが優れているかを考えるのではなく、それぞれの特徴を理解したうえで自社のマーケティング戦略にマッチした手法を取るのがベストプラクティスです。予算に余裕がある場合は、どちらもおこないましょう。
【関連記事】リスティング広告とSEOの違いについてわかりやすく解説
SEOのメリット
SEO対策をおこなった際に得られるメリットを5つ紹介します。
- WEBサイトへの流入数が増加する
- ブランディング効果がある
- 広告費用を抑えられる
- コンテンツが資産になる
- MEO(ローカルSEO)にも効果がある
それぞれ詳しく解説します。
サイトへの流入数が増加する
SEOにおけるもっとも大きなメリットは、WEBサイトへの流入数が増加することです。
検索されることの多いビッグキーワードで検索結果に表示された場合は、オーガニック検索からの流入数が大幅に増加するため、ビジネスでWEBサイトを運営する目的である、「お問い合わせ」や「商品の購入」につながりWEB集客が加速します。
また、検索結果の1位に表示された場合は強調スニペットが表示されるため、より検索画面での露出が高まりクリック数が上昇し、WEBサイトへの流入数が増加するでしょう。
検索エンジンからの流入数を増やすための方法は、SEO以外にもリスティング広告を出向する方法もあります。ただし前述したように、リスティング広告の場合はクリックされるたびに費用が発生します。
そのため、より多くの流入を獲得したい場合は、獲得するクリック数に比例して広告費を増やしていく必要があります。その一方で、自然検索結果に表示させるSEOの場合はクリックされても費用が発生しないため、SEO対策にかけたコストや労力以外の費用が発生することなくWEBサイトへの流入数を増やせます。
SEOでWEBサイトへの流入数を増やすポイントは、ユーザーの検索意図を考慮したコンテンツを作成することです。ユーザーが必要としている回答や、情報を満たす品質の高いコンテンツを作ることで検索エンジンから評価され、さまざまなキーワードでWEBサイトが上位表示されます。
▼ SEO対策で、ブログやホームページのアクセス数を増やしたい方は、以下の記事を参考に取り組んでみてください。
【関連記事】ブログのアクセス数を増やす方法11選!【初心者向けに解説】
ブランディング効果がある
SEO対策で露出を高めることで企業、あるいは自社商品・サービスのブランディング効果を高められます。具体的には、SEO対策によって自社サイトやオウンドメディアが多くのキーワードで上位表示された場合、ユーザーの目に止まる回数が多くなり自社の経営理念やポリシー、自社製品・サービスの認知拡大につながります。
例えば、多くの番組で流れているテレビCMは印象に残るため、自然とその会社や商品のことを覚えてしまった経験が誰にでもあるでしょう。SEOもテレビCMと同じように、ユーザーが検索するたびに表示されることでユーザーに覚えてもらえます。
また、検索結果の上部に表示されていると信頼できるWEBサイトという印象を与えられます。代表的な例を上げるとWikipediaや、最近では価格コムなどが該当します。このようにSEOは、ブランディング効果を高める効果があります。
加えてTwitterやfacebookなど、SNSやYouTubeなどの動画SEOを同時に活用することでさらにブランディング効果を高められます。
広告費用を抑えられる
SEOは、ほかの広告媒体と比較すると広告費を抑えて集客ができます。例えば、リスティング広告はクリックされるたびに費用が発生するため、継続して費用が発生します。
また、リスティング広告は入札制のため、広告を上部に表示させるには競合よりもクリック単価を高く設定して入札する必要があります。そのため、競合他社が広告の入札単価を上げると、ワンクリックにかかる費用が上昇します。
そのほか、折り込みチラシやテレビCMなども定期的に広告配信をしないと広告効果が落ちるため、リスティング広告と同様に継続して費用が発生します。
一方、自分でSEOの知識を学び、自分でSEO対策をおこない自サイトを上位に表示した場合は費用はほとんどかかりません。また、ホワイトハットSEOで上位表示された場合は、継続して上部に表示される傾向があるため、広告のように継続してコストをかけなくても長期的に集客をおこなうことが可能です。
つまり、SEOで上位表示させることは広告費用を抑えて集客ができるということです。
コンテンツが資産になる
作成したコンテンツが資産として活用できる点も、SEO対策のメリットと言えるでしょう。作成したコンテンツはWEBサイトを閉鎖しない限りはインターネット上に残り続けるため、前述したように広告費をかけずに集客ができる資産となります。
ただし、資産にするためにはユーザーにとって価値の高い高品質なコンテンツを作成する必要があります。また、SEO対策で作成した記事コンテンツや動画コンテンツは自然検索からの集客に限らず、商談やプレゼン、SNSの運用、メールマガジンなどさまざまな用途でも利用ができます。
SEM Plusの場合では、作成したコンテンツをもとにホワイトペーパーを作成したり、メールマガジンで配信したりして活用しています。
MEO(ローカルSEO)にも効果がある
特定のエリア内のユーザーを対象とした事業をおこなっている場合、SEO対策をおこなうことでMEO(ローカルSEO)にも良い影響を与えられます。
Googleは自サイトの掲載順位もMEOのランキングを決める要素のひとつだと公言しています。
ウェブ検索結果での掲載順位も考慮に入れられるため、検索エンジン最適化(SEO)の手法も適用できます。
Googleビジネスプロフィールヘルプ:ローカル検索結果のランキングが決定される仕組み
つまり、自店舗の公式ページのSEO対策をおこない検索順位を上げることで、Googleマップや「エリア名+キーワード」で検索した際に表示されるローカルパックにも表示されやすくなるというわけです。そのため、ローカル検索での需要が多い事業の場合、SEO対策をおこなうとMEOにも効果的です。
【関連記事】MEOとは?MEO対策のやり方と順位に影響がある項目
SEOで検索順位が決まる仕組み
SEO対策をおこなうには、検索順位がどのように決まるのか仕組みを理解する必要があります。
▼ 大きくは以下3つのプロセスに分かれていて、上から順にGoogleによってぺージが処理されています。
- クローリング
- インデックス
- 検索結果に表示
記事がクローリングされなければインデックスされることはなく、インデックスされなければランキングされることもありません。つまり、記事が検索画面で上位表示されることを目指すなら、それぞれのプロセスに対して正しくアプローチする必要があるということです。

クローリング
クローリングとは、検索エンジンの情報収集ロボットであるクローラー(Googlebot)が、周期的にWEB上を巡回して新しいURL(WEBサイト・ページ)を検出します。
また、クローリングの際にはGoogle Chromeなどのブラウザで人間がページを見ている画面と同じようにページを再現し、「どのようなコンテンツなのか?」「どのような画像があるのか?」などページ上の情報を確認します。この作業をレンダリングと言います。
クローリングにおいてSEO対策で重要なポイントは、そもそもクローラーがWEBサイトやページを発見しなければ、検索エンジンはWEBサイトやページを認識できないため検索画面に表示されないことです。
そのため、クローラーがどのようにしてページを発見するかを理解する必要があります。
▼ クローラーの巡回について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】クローラーとは?SEOで重要なクロールの仕組みを解説
インデックス
インデックスとは、クローラーが発見したWEBサイト・ページの情報を検索エンジンのデータベースに保管することです。
ただし、検索エンジンはWEB上のすべての情報をインデックスするわけではなく、クロールしたページの情報をもとに、検索結果に表示させる価値があると判断されたページだけをインデックスします。
例えば、第三者のページから丸々コピーしてきたコンテンツや、ユーザーに損害が発生する可能性がある詐欺のサイトなど低品質なページと判断された場合は、検索結果に表示させる価値がないためインデックスされません。
つまり、記事がインデックスされるには、記事がクローラーに発見され、検索エンジンからインデックスするに足る情報が盛り込まれていることが必要です。
▼ Googleがインデックスする仕組みについて、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】Googleインデックスとは?SEOへの影響と確認・登録方法
また、作成したページがなかなかインデックスされない場合は、以下の記事を参考に対処してみてください。
【関連記事】Googleにインデックスされない原因と対処法12選
検索結果への表示
インデックスされたページは、Googleの200以上のアルゴリズムによって評価されます。ユーザーが検索をおこなうと、検索エンジンがインデックスされたページの情報を相対的に評価し、検索クエリと関連性の高い高品質なページを検索結果上に表示させます。
Googleは検索結果の表示について以下のように記載しています。
ユーザーが検索語句を入力すると、インデックスで一致するページが検索され、関連性が高く高品質であると判断された検索結果が返されます。
Google の検索エンジンの仕組み、検索結果と掲載順位について:検索結果への表示
このことから、ユーザーの検索意図を満たすページが検索結果上で重要視されており、ランキングに大きく影響することが分かります。
また、アルゴリズムは公開されていませんが、主に以下の項目が重要と考えられます。
- キーワードとページの関連性
- ページの品質
- 被リンク
- ページエクスペリエンス(操作性や表示速度など)
- ユーザーが検索した位置情報や履歴
Googleの理念とSEOのガイドライン
検索順位が決まる仕組みを理解したら次に、Googleの理念やページの評価規準、SEOのガイドラインをGoogleの公式ページから学ぶことでSEO対策の本質を理解できます。
▼ SEOを始める前に、確認しておくべき公式ページは以下の3つです。
- Googleが掲げる10の事実:Googleの理念
- 検索品質ガイドライン:Googleの評価基準
- 検索セントラル:GoogleのSEOガイドライン
それぞれ解説します。
Googleが掲げる10の事実
「Googleが掲げる10の事実とは」は、Googleが設立して数年後に作成した、 検索における『理念』のようなものです。Googleは、現在でもこの理念を定期的に確認して「事実に変わりが無いか」「提供しているサービスは事実の通りになっているのか」を確認しています。
1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
Google が掲げる 10 の事実
2. 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
3. 遅いより速いほうがいい。
4. ウェブ上の民主主義は機能する。
5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。
7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。
8. 情報のニーズはすべての国境を越える。
9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。
10. 「すばらしい」では足りない。
まだ見たことのない方は、一度目を通してGoogleがどのようなサービスをユーザーに提供したいのかを確認してみてください。Googleが作りたい世界やサービスを理解することで、「どのようなWEBサイトを作ることがGoogleからのSEO評価につながるのか」参考になるはずです。
検索品質評価ガイドライン
検索品質評価ガイドラインとは、検索品質評価者向けに作成されたガイドラインです。
Googleは検索結果の品質を向上させるため、検索品質評価者からのフィードバックをもとに常に検索アルゴリズムを改善しています。
検索品質評価ガイドラインはすべて英語で記載されているため翻訳する必要がありますが、どのようなコンテンツだとPQ(ページクオリティ)が高いのか、または低いのかを事例付きで解説しています。つまり、検索品質評価行化ガイドラインを読むことでGoogleがどのようなページをSEOで評価しているのかを理解できます。
Google は常に、検索結果の利便性向上に努めています。
検索品質評価者と協力して検索品質を向上させる取り組み
具体的には、検索結果の品質を向上させるさまざまな試みを定期的に実施しています。こうした試みを評価する方法の 1 つが、外部の検索品質評価者からのフィードバックです。世界各地の検索品質評価者が、Google が公開している詳細なガイドラインに基づいて厳正な評価を行います。
Google検索セントラル
Google検索セントラル(旧称 Google ウェブマスター)とは、Googleがサイト運営者やウェブマスター向けの公式の情報リソースとサポートセンターです。Googleのアップデートに関する最新情報やSEOに関するさまざまな情報を提供しています。
▼ SEOをおこなう前に以下の2つを確認しておきましょう。
- 検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド
- Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー
検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド
Googleがサイト運営者用に用意したSEOをおこなう上での基本的な説明書です。クローラーにサイトを見つけてもらうための方法から、ページを検索エンジンに最適化させる方法・モバイルフレンドリー・パンくずなど内部対策で必要な項目が詳しく解説してあります。
【参考資料】検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド
ガイドライン違反に注意する
スパムに関するポリシーでは、SEO対策に限らずGoogleの検索エンジンに対してやってはいけないことが記載されています。
意図せずとも、スパム行為をおこなった場合はGoogleからぺナルティを受けてしまいWEBサイトが検索結果から削除されたり、大幅に順位が下落したりします。そのため、事前にスパム行為について理解しておくことが大切です。
【参考資料】Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー
SEOで上位表示させるポイント
SEOで上位表示されるため抑えておきたいポイントを紹介します。SEOでもっとも重要なことは「ユーザーにとって価値と利便性が高いサイト」にすることです。そのために必要なことを5つのポイントに分けて紹介します。
- ユーザーファーストなサイト
- E-E-A-Tを満たしているサイト
- モバイルフレンドリーなサイト
- CWVを満たしているサイト
- Googleのアルゴリズムを理解する
それぞれ解説します。
ユーザーファーストなサイトを作成する
Googleの使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすることです。
先ほど紹介した「Googleが掲げる10の真実」には、Googleが掲げている理念として「ユーザーファーストであることが第一」と書かれています。
ユーザーファーストなサイトとは、「ユーザーの検索意図を満たし価値のある情報を提供する、快適で安全なサイト」です。SEOで大きな成果を上げるためにも、ユーザーの疑問を解決し、ユーザビリティの高いWEBサイトを目指す必要があります。
検索エンジンに評価されるためにコンテンツを作成するのではなく、ユーザーに向けてコンテンツを作成することがSEOでは基本の考えとなります。
E-E-A-Tを満たしているサイトを作成する
「E-E-A-T」とは、General Guidelines(検索品質ガイドライン)で定められているページを評価する上で基準となる概念です。経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼(Trust)の4つの頭文字を取ってE-E-A-Tと呼び、中でも信頼(Trust)が特に重要視されています。
以前はE-A-Tでしたが、2022年の12月に経験(Experience)が追加されE-E-A-Tとなりました。
E-E-A-Tに変更されて以降は「General Guidelines(検索品質評価ガイドライン)」の図のように「経験」「専門性」「権威性」をそれぞれ高めることで「信頼」が高いサイトになり、評価されるということです。

それぞれの項目を車を例に簡単に説明します。
- 専門性
車の修理方法については、個人のブログより車の修理工場が運営しているブログのほうが専門性が高いと言えます。 - 権威性
免許の更新についての情報は運転免許更新センターを運営している警視庁のサイトがもっとも確実な情報元と言えます。 - 経験
車を購入する際はカタログに書かれている数値的な性能だけではなく、実際に運転した際の使い勝手などを参考にしたいユーザーもいるはずです。
いかがでしょうか。解説を見ると専門性・権威性・経験の高いサイトは、「信頼」できるWEBサイトになることが分かります。
今回は車を例に解説しましたが、E-E-A-Tは業種やサイトのテーマによって求められるものが異なるため、WEB担当者の方は自社が運営するサイトの場合は何が重要なのかを考えて強化しましょう。
個人ブロガーの方は権威性を高めるのは難しいですが、実体験を発信することで企業のWEBサイトでは難しい「経験」を強化しE-E-A-Tを高めてみてください。
▼ E-E-A-Tにを高める施策については別記事で詳しくまとめてあります。
【関連記事】E-E-A-Tとは?GoogleのSEOで重要な評価基準を解説
YMYLは特に高いE-E-A-Tが求められる
SEOをおこなう際に、高いE-E-A-Tを求められるジャンルがあります。それは健康やお金など人々の生活そのものに直接影響があるジャンルで、Your Money or Your Lifeの頭文字を取って『YMYL』と言います。
健康やお金に関する情報に間違いがあった場合、ユーザーが直接的な不利益を被る可能性が高いため、YMYLに該当する場合は専門性や権威性が通常のジャンルよりも必要となります。
例えば、病気の治療方法であれば医療に関係のない人物が書いた治療法よりも、病院が運営していて医師が書いた治療法のほうが専門性や権威性が高いと言えます。そのため、現在医療に関するキーワードで検索すると病院が運営しているWEBサイトが検索結果に表示されるというわけです。
【関連記事】YMYLとは?対象ジャンルにおけるSEO対策を解説!
モバイルフレンドリーなサイトを作成する
モバイルフレンドリーとは、スマホページのテキストが読みやすく操作性にすぐれたスマホページを指します。簡単に説明すると「スマートフォンの画面サイズに合った見やすいページ」です。
インターネットで検索するデバイスがPCからスマートフォン中心になり、スマホで情報収集をするユーザーが増えたため、Googleは以下のアップデートをおこないました。
■【2015年】モバイルフレンドリーアップデート
操作性の高いスマホページの検索順位を上昇させるアップデート
■【2016年発表 2021年完全移行】MFI(モバイルファーストインデックス)
スマホページのコンテンツをもとに、インデックスや検索順位の決定をおこなうアップデート
上記アップデート以降は、モバイルページ(スマホページ)を作成していない場合や、モバイルフレンドリーではないページの場合はユーザーフレンドリーではないサイトと判断され、順位が下がる可能性があります。
尚、スマホページが最適化されているかどうかはモバイルフレンドリーテストで簡単に把握ができます。モバイルフレンドリーなスマホページの作成はSEO対策における基本となるため、モバイル対応していない場合は早急に対応しましょう。
▼ 具体的な対応方法については別記事で詳しく解説しています。
【関連記事】モバイルフレンドリーとは?対応方法と確認方法・SEOへの影響を解説
CWV(core web vitals)を満たしているサイトを作成する
CWV(コアウェブヴァイタル)とはページの読み込み時間やページの反応、視覚的な安全性を指標にしたもので以下3つの項目から成り立ちます。
■ LCP(Largest Contentful Paint )ページの読み込み速度
ページの読み込み時間や表示速度を表す指標です。2.5秒以内が推奨されています。
■ FID(First Input Delay):インタラクティブ性
ボタンアイコンをクリックした際の反応速度です。読み込み速度と似ていますが、クリックなどのアクションに対して実行されるまでの時間となります。100ミリ秒未満が推奨されています。
■ CLS(Cumulative Layout Shift ):視覚的な安全性
ページが表示される際におきた画面の「ズレ」を計測しています。画面のズレが大きいと間違ってクリックしてしまう可能性などがあるため、ユーザビリティが低下します。ズレが生じた表示領域の比率×ズレた距離の割合が0.1未満が推奨されています。
CVWは、WEBサイトに訪れたユーザー体験を高める上で重視すべき指標です。また、CVWは2021年におこなわれたページエクスペリエンスアップデートにより検索アルゴリズムに組み込まれ、ランキングに影響するようになりました。
そのため、サイト運営者はSEOの一環としてページの快適性を向上させる施策に取り組む必要があります。
Core Web Vitals は、ページの読み込みパフォーマンス、インタラクティブ性、視覚的安定性に関する実際のユーザー エクスペリエンスを測定する一連の指標です。検索結果でのランキングを上げ、全般的に優れたユーザー エクスペリエンスを提供できるよう、サイト所有者の皆様には、Core Web Vitals を改善することを強くおすすめします。
Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について
Googleの検索アルゴリズムを理解する
Googleのアルゴリズムを理解することで、どのようなWEBサイトがユーザーにとって有益なのかを知れるため、SEO対策ではアルゴリズムを理解することが重要です。
アルゴリズムとは検索順位を決定する際に利用される計算や処理のことで、Googleは検索順位を決定するアルゴリズムのアップデートを年間200以上おこない、ユーザーにとって最適な検索結果になるように常に調整しています。
代表的なアルゴリズムに関してはGoogle検索ランキング システムのご紹介から確認ができますが、ここで説明されているアルゴリズムは200以上あるベビーアルゴリズムのほんの一部であり、Googleはアルゴリズムに関して詳細を公開していません。
そこで重要になるのが、定期的に行われるアルゴリズムのアップデートの内容や過去のアップデートからアルゴリズムを分析することです。
代表的なアルゴリズムのアップデートに関しては、Google Search Status Dashboardからアップデートを行った「日時」「アップデートの詳細ページへのリンク」を一覧で見られるため、定期的に確認してGoogleがどのようなWEBサイトを評価するのか分析しましょう。
▼ 過去にGoogleが行ったアップデートに関してはSEM Plus編集部でまとめています。興味がある方はぜひご確認ください。
【参考記事】Googleアルゴリズムアップデートの歴史(2000年~2022年)
ただし、アルゴリズムだけを追いかけてSEO対策を行うのは注意が必要です。なぜならGoogleの理念は「ユーザーファースト」であり、ユーザーにとって有益なサイトじゃなければGoogleのアップデートにより順位が下がる可能性があるからです。
SEO対策の種類
SEO対策は大きくわけて「内部対策」「外部対策」「コンテンツ施策」の3つの種類に分類されます。

| 施策内容 | |
| 内部対策 | htmlタグ・構造化データの設定 内部リンク・サイト構造の最適化 速度改善・URLの正規化など |
| 外部対策 | 被リンクの獲得 サイテーションの獲得 |
| コンテンツSEO | 検索意図を満たすコンテンツ・ぺージの作成 |
テクニカルSEO(内部対策)
内部対策とは、WEBサイトの内部に対して対策をおこなうことです。内部対策は検索エンジンに対して、ページをクロールしてもらい、コンテンツの内容を正しく伝えインデックスしてもらうための施策です。
例えば、ユーザーが知りたい回答となる素晴らしいページを作成しても、titleタグや見出しタグにページの内容を表すキーワードや文章が入っていなければ、検索エンジンは何について書かれたページなのかを正確に判断できません。
ページが正しく認識されていなければ、SEOで評価ができないため検索結果の上部には表示されない状態となってしまいます。また、ページ自体をクロールしてもらえなければインデックスされることがないため、検索結果に表示すらされません。
そこで、内部対策をおこないページの内容やWEBサイトの構造・ユーザビリティの良さを正確に検索エンジンに伝え、クロール・インデックス・ランキング評価を正しくしてもらう必要があるのです。
内部対策でおこなう施策は数多くありますが、大きく3つの項目に分けられます。
- クロールの促進をおこなう(検索エンジンにサイトを登録する)
- HTMLの最適化(ユーザーとGoogleにページの内容を伝える)
- ページエクスペリエンスの最適化(ユーザーが快適に利用できるサイトにする)
クロール・インデックスの促進
- URL検査ツールを使いインデックス状況の確認をおこないます。
- XMLサイトマップを、サーチコンソールからサイトマップを送信してGooglebotにクロールしてもらいます。
- robots.txtで不要なページへのクロールを拒否します。
- noindexタグを使って、不要なページのインデックスを拒否します。
- URLの正規化をおこなうため、301リダイレクトやcanonicalタグを設定します。
- ユーザー、検索エンジンに関連するページの存在を知らせるため内部リンクを設定します。
- クローラビリティを高めるため、パンくずリストの設置、HTMLサイトマップを作成します。
HTMLの最適化
- ページの内容を要約したタイトルタグを設定します。
- ページの内容を説明するディスクリプションタグを設定します。
- 見出しごとに内容を要約したhタグ(見出しタグ)を設定します。
ページエクスペリエンスの最適化
- Core Web Vitals(CWV)を改善し、ページの表示速度やユーザのアクションに対しての応答時間を改善します。
- SSL化(https化)をおこない、サイトの信頼性・安全性を高めます。
- モバイルフレンドリー対応をおこない、モバイルユーザビリティを改善します。
外部対策
外部対策とは、外的要因によって自サイトの評価を高める施策です。主には、他サイトから自社のサイトに向けて貼られたリンクを多く獲得する「被リンク施策」と、他サイトに自社の情報が引用・言及される「サイテーション施策」があります。

被リンク施策は、Googleのアルゴリズムの一部であるPagerank(ページランク)による評価を利用した手法で、自サイトと関連性が高いWEBサイトから多くの被リンクを獲得することで自サイトのドメインパワーを高めます。
以前よりも被リンク獲得によるSEO効果は少なくなりましたが、今でもランキングに大きな影響を与える項目です。
Google 検索が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断するうえで、膨大なユーザーがウェブサイトに張ったリンクを基準としているからです。Google では、200 以上の要素と、PageRank™ アルゴリズムをはじめとするさまざまな技術を使用して、各ウェブページの重要性を評価しています。PageRank のアルゴリズムでは、ページ間のリンクを「投票」と解釈し、どのサイトが他のページから最高の情報源として投票されているかを分析します。
Google が掲げる 10 の事実:ウェブ上の民主主義は機能する。
サイテーション施策は、自サイトの情報がSNSや他サイトにて引用や言及されることで、サイトの権威性や認知度を高める施策となります。
どちらも、ユーザーにとって価値のある情報を発信し続けることが重要で、よい情報と価値を感じてもらえれば被リンク・サイテーションの獲得につながります。
自作自演でのリンク獲得は、手動による対策というGoogleの重いぺナルティの対象となるためNGです。評価の高いナチュラルリンクを獲得できるように施策をおこないましょう。
【関連記事】
・SEO外部対策とは?意味・やり方と注意点を解説
・SEOにおけるサイテーションとは
コンテンツSEO
コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図にマッチした優良なコンテンツを制作することで、Googleからの評価を高める施策です。現在のSEOにおいては、検索したユーザーのニーズを満たす、信頼できるコンテンツを作成することがもっとも重要です。
理由は、Googleが2019年に自然言語処理の能力を向上させるためのアップデート『BERTアップデート』をおこなったことで、ユーザーの検索ニーズを正確に理解し、検索意図を満たしているコンテンツを正しく評価できるようになったためです。
また、Googleはコンテンツについて『Googleセントラルの検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド』で以下のように解説しています。
人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。ユーザーは閲覧したときに良いコンテンツだと感じると、他のユーザーに知らせたいと思うものです。その際、ブログ投稿、ソーシャル メディア サービス、メール、フォーラムなどの手段が使われます。
検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド:コンテンツを最適化する
このことからもSEOにおいて優れたコンテンツを作成することが重要ということが分かります。
後ほど詳しく解説しますが、優れたコンテンツを作成するにはキーワードから検索意図を読み取り、ユーザーが知りたい回答が何であるのかを最優先に考えて作成します。
また、1つのコンテンツではユーザーニーズを満たせない場合は、検索キーワードに関連するロングテールキーワードでもそれぞれコンテンツを作成し、WEBサイト全体を検索ニーズを満たすように設計していきます。
コンテンツSEOは継続して高い効果が見込めるため、スタートアップ企業や集客にコストをかけられない会社、中長期的な施策に取り組める会社におすすめの手法と言えます。
【関連ページ】
【2023年最新】コンテンツSEOとは?メリットや6つの手順、効果を高めるやり方まで完全網羅!
追加のSEO施策が必要となるサイトの種類
前項目で一般的なSEO対策の種類について説明しましたが、サイトの種類によってはSEOをおこなう際に追加の施策が必要となり、より高いSEOスキルが求められます。
■ ECサイトSEO
ECサイトのSEOでは以下項目の最適化が重要です。
「カテゴリページ・製品ページ、製品の口コミ、製品ページの正規化、内部リンク構造、メニュー設計、製品画像、商品一覧ページ、動的ページ」
■ オウンドメディアサイトSEO
オウンドメディアサイトのSEOでは、以下項目の最適化が重要です。
「著者情報、編集ポリシー、内部リンク、カテゴリ設計、検索意図の網羅、内部リンク、見出しごとの画像」
■ データベース型サイトSEO
データベース型サイトのSEOでは、WEBサイト内検索によって生成される大量の動的ページのインデックスをコントロールし、検索結果に表示させたいページを効率よくクロールさせることが重要です。htmlの知識だけではなく、プログラミングの知識が必要となります。
■ ニュースサイトSEO
ニュースサイトのSEOでは、インデックスされるまでの速度が重要です。競合のニュースサイトよりも早くインデックスさせて、Google Discover、Googleニュースなどに表示されるように対策をおこないます。
■ 海外SEO
海外SEOとは、さまざまな国や言語を対象としたSEO対策です。対象となる国の言語に翻訳したページを作るだけでなく、その国の検索結果にあわせたコンテンツ作成や、対象となる国でシェア率の高い検索エンジンに対応したSEOをおこなう必要があります。
テクニカルSEO(内部対策)のやり方
テクニカルSEOとは、ページの内容やサイトの構造を検索エンジンに正確に伝えるための施策です。どんなに良いコンテンツ・ぺージを作ったとしても、検索エンジンに正しく認識してもらえなければ評価されません。
そのため、SEOの基本であるテクニカルSEO(内部対策)を理解しましょう。
▼ SEO対策の基本となる項目は以下の10項目です。
- titleタグを設定する
- メタ・ディスクリプションタグを設定する
- hタグ(見出しタグ)を設定する
- 内部リンクの設定
- altタグの設定
- URLの正規化
- 構造化データ
- SSL化(https化)
- robots.txtの設定
- ページ速度の改善
①titleタグを設定する

titleタグは、検索エンジンがページの内容を確認するための重要な要素です。検索エンジンは、ユーザーが検索したキーワードと関連が高いページを検索結果に表示させます。そのため、ページの内容を表すtitleタグを設定することで、SEO効果を高められます。
また、設定したtitleタグは検索結果に表示されるためクリック率にも大きく影響します。titleタグの設定は、SEO対策の基本中の基本なので必ず設定してください。
titleタグ設定でSEO効果を高めるポイント
- ページの内容を表すキーワードを必ず入れる
- 先頭に重要なキーワードを配置する
- titleタグの文字数は30文字前後に収める
- ページごとに独自のtitleタグを設定する
▼ SEOに効果的なタイトルタグの設定方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】SEOに強いtitleタグ(タイトルタグ)の書き方・文字数とは?
②メタ・ディスクリプションを設定する
meta descriptionタグ(メタディスクリプションタグ)とは、ページの内容を説明する概要文です。こちらもtitleタグと同様に検索結果に表示されるためクリック率に大きく影響しますが、titleタグと違いSEOの効果はほとんどありません。
ただし、100文字程度表示されるためユーザーが興味を示す説明文を入れることでクリック率を高められるため、WEBサイトへの流入数増加が期待できます。
meta descriptionの設定でSEO効果を高めるポイント
meta descriptionにキーワードを含めて、ユーザーがクリックしたくなるような文言を意識しましょう。ユーザーへの訴求力を高めるには、検索結果に省略されずに表示されるように設定をする必要があります。meta descriptionタグに含めるテキストの文字数は、100文字程度に収めるのが理想です。
▼ SEOに効果的なメタディスクリプションタグの設定方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】メタディスクリプションとは?文字数と書き方の例文・SEOの効果
③hタグ(見出しタグ)を設定する
hタグに対策キーワードを設定しましょう。hタグとは「見出し」としてページ上に表示されるタグで、ユーザーと検索エンジンにコンテンツ内の各セクション内容がどのようなものかと、コンテンツ内の構造を伝える役割があります。
titleタグがページの大テーマであるのに対して、hタグはページ内の大見出し・中見出し・小見出しとなります。hタグにキーワードを設定することで、どのような内容について記載されているページなのかを、より正確に検索エンジンに伝えられるためSEO効果が高まります。
hタグの設定でSEO効果を高めるポイント
■ 簡潔に説明をまとめたシンプルな見出しを作成する
ユーザーが見ただけで、見出し内のコンテンツの内容が分かるように設定します。
■ 使用する見出しの階層を正しく設定する
h1は大見出しとしてページの概要を記載し、h2はページ内の中見出しとしてセクションを記載します。h3は小見出しとしてセクション内のポイントを記載します。
■ h1タグは原則1つだけ設定する
ページの概要を検索エンジンに伝えるタグの中で、h1タグはtitleタグの次に重要なタグです。そのため、h1タグは1つだけ設定します。
▼ SEOに効果的なhタグの設定方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】h1タグとは?使い方とタイトルとの違い・SEO効果を解説
④内部リンクの設定

自分のWEBサイト内のページを繋ぐリンクのことを内部リンクと言います。検索エンジンは内部リンクが多く集まっているページを重要なページと判断し評価するため、メインコンテンツに内部リンクを集めることでSEO効果を高められます。
また、検索エンジンは内部リンクを辿って新しいURLを発見しインデックスさせます。検索エンジンのクローラビリティが向上するような内部リンク構造にすることで、インデックスの促進につながります。
内部リンクを設定する際は、関連するページ同士を相互リンクさせることが基本です。
関連するページへの内部リンクがあることで、ユーザーの利便性が高まり、ページの離脱防止やWEBサイトの評価につながります。
内部リンクの設定でSEO効果を高めるポイント
- アンカーテキストはリンク先の内容が分かる内容にする
- 上層ページ、同一階層のページ、下層ページへのリンクを設定する
- 関連性の高いページに内部リンクを設定する
- 検索エンジンが発見できないぺージが発生しないようにする
- メイントピックや重要ページに内部リンクを集める
内部リンクを設定する場所
- HTMLサイトマップ
- パンくずリスト
- グローバルナビゲーション
- フッターメニュー
このようにWEBサイト内で関連するページや親子関係にあるページに対して、適切な内部リンク構造を構築することがSEO対策においては重要です。

【関連ページ】
・内部リンクとは?SEO効果を高める貼り方のコツ
・サーチコンソールから内部リンクを確認する方法
⑤altタグを設定する
altタグとは、画像の内容を説明するためのhtmlタグです。検索エンジンは画像の内容を正確に把握できないため、alt属性に設定された代替テキストを参考にして画像情報を判断します。
alt属性を記述することで、テキストと関連性の高い画像がページにあることを検索エンジンに正しく伝えられるためSEO効果が高まります。ただし、alt属性に対して特定のキーワードだけを大量に詰め込むような行為は、スパム判定を受ける可能性があるので絶対に行ってはいけません。
altタグの設定でSEO効果を高めるポイント
- 画像の内容を簡潔に記述する
- キーワードを詰め込み過ぎない
- 画像の内容と関連性が高い文章を設定する
- 同じ画像を使用する際は同じ文章を設定する
▼ SEOに効果的なaltタグの設定方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】alt属性とは?書き方と設定方法・SEO効果について解説
⑥URLの正規化をおこない重複コンテンツを防ぐ
URLの正規化とは、内容が同じページのURLをひとつに統一することを言います。
URLの正規化がおこなわれていない場合、検索エンジンから重複コンテンツと判断され、ページの評価が分散してしまいSEO対策においてWEBサイトが低評価になる可能性があります。
URLの正規化ができていないケースには、「httpとhttps」「wwwの有無」「index.htmlの有無」「URL末尾のスラッシュの有無」「パラメータの有無」などがあります。
このようにページの内容が同じにも関わらず異なるURLが存在している場合は、正規URLを決めた上で301リダイレクトを設定してURLを正規化しましょう。
内容が同じURLをリダイレクトで統合できない場合は、canonicalタグを使ってURLを正規化して対処します。アパレルショップで色違いのページを作成する必要がある場合などにおこないます。
【関連記事】URL正規化とは?正規化が必要な7つの具体例と設定方法を解説
⑦構造化データ
構造化データとは会社情報や、口コミ、FAQなどの項目を検索エンジンが理解しやすいように規則に従いhtmlタグを設定することを指します。
例えば、だれが書いたコンテンツなのかを検索エンジンに正しく伝えるために、コンテンツの著者情報・所有者情報を、構造化マークアップで実装し信頼性を高めます。また、構造化をおこなうことでリッチリザルトに表示されクリック率が高まる可能性があります。
構造化データは、WEBHTMLを直接マークアップする方法と、構造化データツール(データハイライター)の2種類の方法があります。直接ランキングに関連する施策ではありませんが、検索結果画面の占有率が高まるためSEO対策として取り組みましょう。
⑧SSL化(htttps化)
Googleは、ユーザーが安全にWEBサイトを閲覧できるように、セキュリティ機能で保護されているhttps対応のWEBサイトを優位にするランキングアルゴリズムを導入しています。
また、SSL化されていないページの場合、警告マークが表示されユーザー離脱につながる恐れがあるため必ずSSL化しておきましょう。SSL化はE-E-A-Tの「信頼」を高める施策となるため、SEO対策をおこなう場合は必須になる施策です。
▼ SSL化について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【参考記事】SSL化(https)とは?SEO効果や検索順位への影響について解説
▼ SSL化の手順について詳しく知りたい方は別記事をご覧ください。
【参考記事】
・WordPressのSSL化(HTTPS化)の手順・設定方法を解説
・ロリポップでワードプレスのhttps化(SSL)とリダイレクト設定をおこなう手順
・エックスサーバー常時SSL・https化をWordPressでおこなう手順
⑨robots.txtの設定
robots.txtとは、クローラーのアクセスを許可するページ・アクセスを拒否するページを伝えるためのファイルです。基本的に、ほとんどのサイトではGoogleのクローラーであるGoogle botがアクセスできるように設定しておけば問題ありません。
ただし、クローラーが巡回するページの数や頻度はWEBサイトごとに上限が決まっています。動的ページが数万ページ生成されるような大規模なWEBサイトの場合は、重要なページに対して優先的にクローラーが巡回するように、不要なページのクローリングをrobots.txtで拒否します。
大規模サイトのSEO対策では、インデックスさせたいページを検索エンジンが効率よくクロールできるようにするのが重要です。
▼ robots.txtの設定方法やSEOでの活用方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】robots.txtとは?意味・効果・設定方法について解説
⑩ページ速度の改善
ページの表示速度は、Googleの検索アルゴリズムにおける検索順位を決める要素のひとつのため、表示速度の遅いWEBサイトはSEOではマイナスの要因となります。
特にモバイルサイトにおいては表示速度が重要視されていて、Googleは2018 年7月より、「ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用する」と発表しています。
【参考ページ】
Google検索セントラル:ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します
そのため、CWV(Core Web Vitals)の改善を行い、ページの表示速度をユーザーが快適に使えるように改善しましょう。
ページ速度を改善する方法
ページの速度を改善するにはツールを使い、自サイトの表示速度がユーザーの満足度を下げる状態になっているかを確認することから始めます。
サーチコンソールのエクスペリエンスレポ―トから「ウェブに関する主な指標」を開き、CWVに関するWEBサイトの状態を「良好」「改善が必要」「不良」の3種類のステータスで表示します。

「良好」以外のステータスになっている場合はページ速度の改善が必要です。具体的な改善箇所については、Googleが提供しているPageSpeed Insightsから確認できます。
PageSpeed Insightsを開いてURLを入力すると、項目ごとに点数が付けられるため、改善が必要な箇所を把握できます。項目ごとに具体的な改善方法が表示されるので、改善方法に従ってページを修正します。
コンテンツ施策(コンテンツSEO)のやり方
SEO効果の高いコンテンツを作成するための方法を解説します。この項目で重要なことは、Googleではなくユーザーを意識してコンテンツを作成することです。
SEM Plus編集部が本メディアのコンテンツを作成する際に実践しているコンテンツ施策では、大きく以下4つを意識して取り組んでいます。
- キーワード選定をおこなう
- 検索意図を満たすコンテンツを作成する
- ユーザーが満足するコンテンツを作成する
- 関連のあるトピックを網羅する
それぞれ詳しく解説します。
キーワード選定をおこなう
キーワード選定は、自社サイトで提供しているサービスや商品を必要とするユーザーが、どのような検索キーワードをGoogle検索で入力するかを考えることが重要です。まずは、自社サイトを探すユーザーの視点に立ってキーワードを洗い出しましょう。
STEP1. キーワードを洗い出す
ターゲットとなるユーザーが自分のサイトを探すときに、どのようなキーワードで検索をするか想像しながら、たくさんのキーワードをリストアップします。Googleが無料で提供しているGoogle Adwordsの「キーワードプランナー」を使うと、簡単にキーワード候補を洗い出せます。
ビッグキーワードだけでなく、2語を組み合わせたロングテールキーワードも洗い出しましょう。
▼ キーワード選定はツールを利用すると効率的に行うことができます。別記事でまとめていますので興味がある方はご覧ください。
【関連記事】
・キーワード掛け合わせツール6選!SEOのキーワード調査を効率化する無料ツール
・無料キーワード選定ツール6選!おすすめのツールを紹介
STEP2. キーワードをグルーピングする
洗い出したキーワードごとに検索意図を考えて、キーワードをグルーピングします。
例えば「SEO費用」「SEO価格」はどちらも「SEO対策にかかる費用を知りたい」という検索意図のため、1つのコンテンツでそれぞれの検索意図を満たせます。
グルーピングしたキーワード群ごとに、1つのトピック(ページ)と考えてコンテンツを作成することでサイト内でのコンテンツの重複を防げます。
キーワード選定の注意点
月間検索ボリュームを参考にキーワード選定をするケースを未だにみかけますが、検索ボリュームが多くても自社サービスに関連性がなかったり、WEBサイト内に検索ニーズを満たすコンテンツを用意できない場合は、SEO対策をおこなっても上位表示される可能性はほとんどなく意味がありません。
繰り返しになりますが、検索ボリュームが多いか少ないかではなく、自社のWEBサイトに興味を持つユーザーが検索するキーワードは何かを考えて選定しましょう。
▼ キーワード選定については別記事でまとめてるので、詳しく知りたい方はご覧ください。
【関連記事】SEOキーワード選定のやり方・コツを徹底解説
検索意図を満たすコンテンツを作成する
ユーザーの検索意図に合致したコンテンツを作成することは、コンテンツ作成の中でもっとも重要な要素です。ユーザーが求める情報を提供し、そのニーズや疑問を解決できるコンテンツを作成することが目標となります。
検索ユーザーは、自分の疑問や関心事に対する回答を求めて検索を行います。したがって、検索意図を満たすコンテンツとは、ユーザーの「質問」に対する「回答」が含まれたコンテンツのことです。
具体的な対策キーワードを選定したら、そのキーワードに関連するユーザーが求めている回答を的確に考える必要があります。ユーザーの視点に立ち、自分が同じ質問を持った場合にどのような回答が最適で有益であるかを考えましょう。
検索意図を把握する方法
- 検索結果の1ページ目に表示されるコンテンツの内容から考察する
- ユーザーにインタビューやアンケートをおこなう
- SNSでキーワード検索をしてユーザー同士のディスカッションから考察する
- 関連キーワードから考察する
- Chat GPT等のAIツールで確認してみる
など、複数の方法を使って総合的に判断しましょう。
▼ 検索意図についてや調べ方は別記事で詳しく解説しているのでそちらをご覧ください。
【関連記事】検索意図とは?考え方と種類について解説
ユーザーが満足するコンテンツを作成する
検索意図を網羅したら、次に「ユーザーが満足するコンテンツ」を作成します。
Google検索セントラルの「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」ページには以下のように記載されています。
コンテンツと品質に関する質問
有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成
・コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。
・コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。
・コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。
・コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。
ここから分かることは、ただ検索意図を網羅しただけではユーザーを満足させられないことです。
検索結果の1ページ目に表示されている記事を参考にしただけのコンテンツには、ほとんど価値はありません。なぜならユーザーからみると、同じようなコンテンツであれば既に上位に表示されているWEBサイトだけで十分だからです。
ユーザーの満足度を高めるために、SEM Plusで取り組んでいることを3つ紹介します。
一次情報を入れる
自社だけが持つデータや独自におこなったアンケート結果など、インターネット上にはない情報を積極的にコンテンツに含めましょう。
また、新しくリリースされた商品やサービスの使い方なども、インターネット上に情報がない場合は一次情報として有効です。
画像・動画を入れる
オリジナルの画像や動画もユーザーの満足度を高められます。例えば、「商品についての説明文」「サービスの利用手順」「図解での説明」などでオリジナルの画像を入れてテキストだけではなく、視覚的にもユーザーに分かりやすく伝えるように工夫します。
アンケート結果や調査データなどは画像があるほうが読みやすくなり、離脱防止にもつながります。また経験や体験に関する画像は実際に体験した証拠にもなるため、E-E-A-Tを高めることにもつながります。
コンテンツの目的・情報源を明確にする
「だれが何の為にどういう目的で作ったコンテンツなのか」を明確にすることで、信頼できるコンテンツになります。
例えば、「コンテンツを作った著者や監修者のプロフィールを掲載する」「どういった会社が運営しているサイトなのかを明確にする」「会社・著者の実績を明確にする」ことでユーザーはコンテンツの内容を信頼できます。
また、コンテンツ内の情報の正確性をユーザーに伝えるために、公的機関が運用するWEBサイトや専門家が運営する、権威性の高いWEBサイトを引用元としてリンクすることも信頼を高めるために有効な手法です。
情報の鮮度を高める
どんなに良いコンテンツでも、古い情報が掲載されている場合はユーザーの満足度を高められません。
例えば、以下に該当する項目は常に最新の情報に入れ替えるようにしましょう。
- 制度や法律の改正
- ツールの機能アップデートや商品のアップデート
- サービス内容の変更
特に自社製品やサービスに関する最新のトピックに関しては、常にコンテンツをアップデートをしないと自社の評判を落とすことにつながります。
また、最新情報にアップデートしたらtitleタグに、「〇〇 変更について解説」「〇〇 新制度とは」などキーワードを入れることで、新しい情報を探しているユーザーが検索した際にページがヒットしやすくなります。
関連のあるトピックを網羅する
メイントピックに関連するトピックを網羅するようにページを作成することで、WEBサイトの専門性が高まりSEO効果が向上します。例えば、SEOのオウンドメディアであれば「被リンク」「titleタグ」「Googleアップデート」など、SEOを探すユーザーが検索する可能性の高い関連トピックの記事を増やします。
これはメディアサイトに限った話ではなく、サービスサイトにおいても同様に効果的な手法です。例えば、リフォームのコーポレートサイトであれば、「施工事例」「対応エリア」「お客様の声」「費用」「施工の流れ」などが関連トピックに該当します。
実際にSEM Plusでは、MEOに関連するコンテンツを70ページ近く作成したことで、「MEO」や「MEO会社」のようなビッグキーワードでも、運用開始から1年以内に検索結果の1ページ目に表示されています。
SEO外部対策のやり方
外部対策の具体的なやり方は、被リンクとサイテーションの獲得です。特にSEO対策においては被リンクの獲得が重要とされ、被リンクの獲得によりWEBサイトのページランクが高まるだけでなく、E-E-A-Tにおける「権威性」を高める効果が期待できます。
被リンク評価を高めるために重要なポイントを3つ解説します。
①関連性や信頼の高い被リンクであること
自サイトと関連性が低いサイトからの被リンクや、信頼性の低いサイトからの被リンクを獲得してもSEOの評価はほとんどありません。
なぜならGoogleは、
・関連する分野で最新、かつ専門的な情報を発信するから被リンクを貼られているサイトは、同じく専門的だと考えられる。
・信頼性の高いサイトから被リンクを貼られているサイトは同じく信頼できる。
・多様性のあるサイトから被リンクをたくさん貼られているサイトは人気である。
といったように、被リンク元の情報をもとにリンク先のWEBサイトの価値を測り、評価しているからです。
②被リンクとして有効であること
被リンク評価を得るには、有効なリンクタグで記述されている必要があります。被リンクを獲得してもリンクタグに「rel=”nofollow”」「rel=”sponsored”」「rel=”ugc」のいずれかが記述されている場合は、検索エンジンがリンク先のページをクロールしないためSEO効果は無効となります。
ただし、nofollowの設定されていない有効な被リンクを獲得できるかどうかは、WEBサイト運営者側でコントールできることでないため気にしなくても問題ありません。自サイトから外部サイトへリンクをする際に、リンク先を評価したくない場合は設定しておきましょう。
【関連記事】nofollowとは?使い方と設定するケース・SEO効果について解説
③自作自演での被リンクを行わないこと
被リンク評価を高めるために被リンクを購入したり、ランキングの操作目的のために自身で被リンクを作成することは不正行為であり、Googleのガイドライン違反になるためNGです。自作自演での被リンク獲得はSEO効果がないだけでなく、ペナルティの対象となる可能性もあります。
被リンク獲得によってSEO効果を高めるには、自然に獲得したナチュラルリンクである必要があります。
被リンクの獲得方法
被リンクを獲得するには、大前提として第三者がリンクしたいと思うコンテンツを用意する必要があります。そのためには、一次情報の掲載や、インフォグラフィックスなどを入れるなどして、感度の高いサイト運営者が自身のメディアやブログで紹介したくなるようなコンテンツを作成しましょう。
▼ コンテンツを作成したら以下の方法でコンテンツを拡散します。
- プレスリリースで配信する
- SNSで情報発信をする
多くの人に作成したコンテンツが認知されることで、被リンク獲得のチャンスが広がります。特に話題のトピックに関するデータやアンケート結果を一次情報としてプレスリリースで発信すると、同ジャンルのメディアが取り上げてくれるケースが多いです。
上記以外にも、
- リンク切れしているWEBサイトに連絡をして自社にリンクを変えてもらう
- 他社メディアに寄稿して、著者情報として自社にリンクしてもらう
- 無料ツールを作成して、メディアに取り上げてもらう
など、被リンクを獲得する方法はさまざまです。
繰り返しになりますが、評価の高い被リンクを獲得して、SEO効果を高めるためには関連性の高いナチュラルリンクの獲得が必要不可欠です。
▼ 被リンクを獲得する方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【関連記事】被リンクとは?被リンクを増やす18の獲得方法
やってはいけないSEO施策
SEO対策をおこなう場合、Googleの検索セントラルに記載されているGoogle ウェブ検索のスパムに関するポリシーに該当する施策はペナルティの対象となるため、やってはいけません。
具体的には、ユーザーと検索エンジンに別々のコンテンツをみせるクローキングやワードサラダによって自動で生成されたコンテンツの作成、過剰な相互リンク集への掲載や被リンクの売買によるリンクスパム、隠しテキストや隠しリンクが該当します。
これらの行為を総称してブラックハットSEOと呼び、ウェブスパムとして判断された場合は手動による対策ペナルティによって、WEBサイト全体の検索順位の大幅な低下やインデックスから削除されるなど厳しい罰が課せられます。
意図せずブラックハットSEOをおこなわないように、以下の行為に該当しないように注意してホワイトハットなSEO対策をおこなってください。
【ブラックハットSEOに該当する行為】
- Googleの方針に背いた手法を用いて検索順位を上げる
- ユーザーの利便性を無視した不正な方法を使う
- 検索エンジンのアルゴリズムの脆弱性をつく
▼ SEOスパムについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【参考記事】SEOスパムとは?スパムに該当する行為を全て解説
SEOをおこなう上で導入すべきツール
SEO対策をおこなうには、自サイトの現状を把握する必要があります。
現在の状況を把握するにはGoogleが無料で提供している、
- Google Search Console
- Google Analytics
を導入するのがおすすめです。
自サイトの分析をおこなうSEOツールは被リンク調査をおこなうahrefs(エイチレフス)や、WEBサイト内のhtmlタグの設定を一覧で閲覧できるScreming Frog(スクリーミングフロッグ)など、各社がさまざま様々なツールを提供しています。
本記事では、Googleが無料で提供している「Google Search Console」と「Google アナリティクス」を紹介します。
Google Search Console
Google Search Console(Googleサーチコンソール)を導入することで、自サイトが検索エンジンにどのように認識されているかや、検索結果においてのパフォーマンス・被リンク状況など、SEOをおこなう際に重要となる指標を把握できます。
具体的には、検索パフォーマンスレポートに自サイトに流入があった検索クエリや表示回数、平均掲載順位が表示されるため、現在の順位状況や改善すべきキーワード候補を洗い出せます。
また、ページインデックス登録レポートからインデックス状況を把握できるため、クロールエラーの確認やURL検索ツールから、インデックス登録リクエスト・サイトマップの送信などインデックスのコントロールをおこなえます。
他には、ページエクスペリエンス(ユーザーにとって快適に閲覧できるページになっているかの指標)の把握や、内部リンク状況などもレポート化されるため、ページの速度改善や内部リンク施策などテクニカルな施策をおこなう際に役立ちます。
【関連記事】サーチコンソールとは?初心者でもできる使い方と設定手順
Google Analytics
Google Analytics(グーグル アナリティクス)を導入することで、自サイト内のユーザー行動に関するさまざまなデータを計測できます。
例えば、流入元経路を見れば、ユーザーがオーガニック検索で流入したのかSNSやブックマークからの流入なのかを確認できるため、SEO対策をおこなったことでオーガニック検索からの流入が増えているかどうか効果検証をおこなえます。
また、ユーザーの離脱率や直帰率の高いページを洗い出して、ユーザーの検索意図を考慮したページに作り変えるなど、コンテンツSEOのリライト施策にも活用ができます。
Google AnalyticsとGoogle Search Consoleは連携できるため、同時に導入しましょう。なお、Googleタグマネージャーを使うと導入から連携までスムーズにおこなえます。
【関連記事】
Googleタグマネージャーでのアナリティクス(GA4)とサーチコンソールの登録・連携方法
SEOの事例と実績
これまで3,000社以上のSEO対策を実施してきた経験をもとに、28業種をピックアップして業種ごとに最適なSEO対策のやり方や、キーワード選定の方法・実績をまとめています。
1. 【買取業界必見!】買取関係のSEO対策・ネット集客の方法
2. 【外壁塗装業界必見!】1位にする外壁塗装のSEO対策方法
3. 【整体業界必見!】整体・整骨院関係のSEO対策・キーワード選定方法
4. 【スマホ修理業界必見!】スマホ・iphone修理関係のSEO対策・キーワード選定方法
5. 【注文住宅業界必見!】注文住宅関係のSEO対策・キーワード選定方法
6. 【歯科業界必見!】歯医者関係のSEO対策・キーワード選定方法
7. 【美容院・ヘアサロン業界必見!】美容院関係のSEO対策・キーワード選定方法
8. 【清掃業界必見!】ハウスクリーニング関係のSEO対策・キーワード選定方法
9. 【不用品回収業者必見!】不用品回収関係のSEO対策・キーワード選定方法
10. 【弁護士事務所必見!】弁護士事務所関係のSEO対策・キーワード選定方法
11. 【学習塾必見!】塾関係のSEO対策・キーワード選定方法
12. 【トレーニングジム必見!】パーソナルジム・トレーニングジム関係のSEO対策・キーワード選定方法
13. 【結婚相談所必見!】結婚相談所関係のSEO対策・キーワード選定方法
14. 【探偵業界必見!】探偵関係のSEO対策・キーワード選定方法
15. 【美容整形・皮膚科必見!】美容クリニック関係のSEO対策・キーワード選定方法
16. 【エクステリア業者必見!】エクステリア・外構工事関係のSEO対策・キーワード選定方法
17. 【オーダーメイド結婚指輪業者必見!】オーダーメイド結婚指輪関係のSEO対策・キーワード選定方法
18. 【カーショップ必見!】ガラスコーティング・板金塗装関係のSEO対策・キーワード選定方法
19. 【ダイビング業者必見!】ダイビング関係のSEO対策・キーワード選定方法
20. 【ペット葬儀社必見!】ペット葬儀関係のSEO対策・キーワード選定方法
21. 【写真館・フォトスタジオ者必見!】フォトスタジオ関係のSEO対策・キーワード選定方法
22. 【葬儀社必見!】葬儀関係のSEO対策・キーワード選定方法
23. 不動産業界のSEO対策手法とキーワード選定方法
24. 【産婦人科必見!】婦人科病院のSEO対策・キーワード選定方法
25. 【記念品業者必見!】ノベルティ・記念品関係のSEO対策・キーワード選定方法
26. 【引越し業者必見!】引越しのSEO対策・キーワード選定方法
27. 【行政書士必見!】行政書士事務所関係のSEO対策・キーワード選定方法
28. 専門学校のSEO対策のやり方とキーワード選定方法・対策事例
SEOで成果を出すには、業種により対策すべきポイントを抑えることが重要です。これからSEO対策を始める方は、自身の業種のSEO対策事例を確認のうえ進めてみてください。
▼ 下記記事では、業種以外にもBtoBがメインの事業となっている会社向けに、BtoBサイトにおけるSEOのやり方を事例を踏まえて紹介しています。
【関連記事】BtoBのSEO対策を成功させるポイント・基本解説から活用できるツールまで紹介
まとめ
SEO対策を成功させる為には、Googleの考え方を深く理解することが大切です。Googleの「ユーザーファースト」の理論は基本的に変わることはありませんが、検索アルゴリズムは「ユーザーにより理想的な検索結果」を提供するために、今後も頻繁に改善を加えられていくと考えられます。
弊社、オルグロー株式会社のSEO対策サービス「ホワイトリンク」は、Googleアップデートに左右されず、いち早く最新のアップデートに対応した施策を行っています。
SEO対策でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。SEO経験豊富なスタッフが貴社WEBサイトの課題を分析し、ご提案いたします。
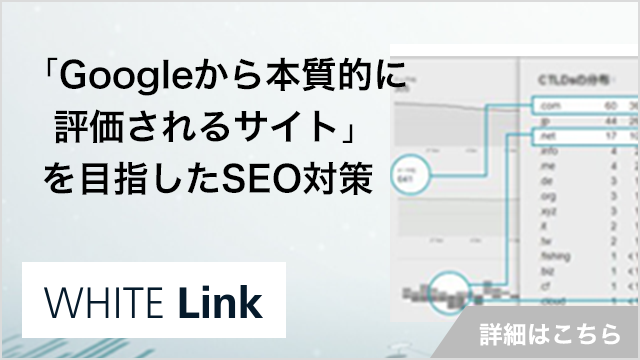
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














