SEOスパムとは?種類と対策方法を解説

SEOスパムとはGoogleの定めたガイドラインに違反した不正な行為の事です。SEOスパムを行うとペナルティを受け、検索結果に表示されなくなるなど非常にリスクがあります。どのような行為がSEOスパムに該当するのか解説していきますので、正しく理解してペナルティを受けることがないようにしましょう。
SEOスパムとは?
SEOスパムとは、Google検索エンジンから不正と判断される過剰なSEO対策のことを指します。
具体的には、隠しリンクや隠しテキストの埋め込み、自動で生成されたコンテンツを使用するなど、Googleのガイドライン上で禁止されている事をおこなう行為がSEOスパムの対象となります。
SEOスパムと判断された場合は、Googleから「危険性が高いサイト」とみなされ「スパムサイト」として認識されます。スパムサイトと認識された場合は、検索結果に表示されなくなったり、Googleのデータベースからサイトが削除される(インデックスから削除)など厳しいペナルティの対象になります。
SEOスパムと判断されないように、どのような行為をGoogleはスパムとみなすのかをきちんと理解しておくことが大事です。
代表的なSEOスパム一覧
ではどのような対策がSEOスパムとして認識されるのか、本項では解説していきます。
いずれの手法も、不当にGoogleから評価を得るために生み出されたものです。先述した通り、ペナルティを受ける可能性があるので正しく理解して、悪徳なSEO手法には決して手を染めない様にしましょう。
クローキング
クローキングとは、検索エンジンと検索した人間のユーザーの、それぞれに別のコンテンツを認識させることを指します。IPアドレスやユーザーエージェントを活用し、ページの訪問者が人間なのか検索エンジンのクローラーなのかを見極めて、全く別のページを表示させます。
人間には画像や写真がメインのページを、クローラーにはキーワードを埋め込んだテキストがメインのHTMLページを認識させる。などが例として挙げられます。
クローキングは、ユーザーに提供する情報とクローラーに提供する情報が異なるため、適切なコンテンツの評価が出来ません。そのためクローキングはSEOスパム行為とされています。
誘導ページ(ドアウェイページ)
誘導ページとは、サイトを訪れたユーザーを特定のサイトに誘導することを目的として用意された低品質なページの事です。Googleはユーザーの検索ニーズに応えるために、最も関連性が高く有益な検索結果を提供しようとしています。
そのため、ランディングページのような広告から商品購入を促したい場合に作られるページや、SEOを目的とした「商圏エリア+サービス」のようなキーワードに対応させるために、ページ内の一部キーワードだけ変えて量産したページなどは、独自の情報をユーザーに提供できない、もしくはユーザーの疑問・不安を解消できていないとGoogleから判断されるとSEOスパムとみなされる可能性があります。
商品の購入ページへの誘導や、エリアに対応したページを作ることが悪いという訳ではありません。ページがユーザーにとって存在価値を持てるようにコンテンツを作成しましょう。
隠しテキストと隠しリンク
隠しテキスト・隠しリンクとは、検索ユーザーがブラウザ上でサイトを閲覧した際に、見えないようにコンテンツやリンクを設置する行為です。
具体的には、人間がブラウザを見てもテキストを確認できないように、フォントサイズを極端に小さくしたり、テキストの色を背景と同じにしたりすることで検索エンジンにのみ任意のコンテンツを読み込ませる手法です。
これはクローキングと同様に、人間と検索エンジンとで提供する情報が異なるため、コンテンツの正当な評価を妨害します。よって隠しテキスト・隠しリンクはSEOスパム行為の対象となります。
キーワードの乱用(詰め込み)
特定のキーワードをページ内に過剰に詰め込むことも、SEOスパムに該当します。キーワードスタッフィングとも言われ、metaタグやtitleタグ、altタグに順位を上げたいキーワードを大量に入れ込むことでページ内でのキーワードの出現率を高めます。
これにより、
- 専門性の高いサイトだと検索エンジンが誤認する
- ユーザーが検索したクエリと関連性のが高いサイトだと検索エンジンが誤認する
といったことを狙ったSEOスパム行為となります。
この手法はGoogleの検索アルゴリズムの精度が上がり、現在では通用しなくなってきています。意図せずキーワードの乱用をおこなっていると判断されないためにも、過剰にキーワードを詰め込んでいないか確認しましょう。
リンクスパム
リンクスパムとは、自作自演や過剰な相互リンクによってランキングを操作しようとする行為を指します。Googleは、WEBサイトが獲得している被リンクの量や質・関連性を元にサイトの人気度や重要度を評価する考え方である「リンクポピュラリティ」を基本としています。
リンクスパムはこの「リンクポピュラリティ」の考え方に基づくアルゴリズムの評価を悪用した、リンクによる不正な手法全般のことです。
具体的には、
- リンクの売買
- 過剰な相互リンク
- プログラムによって自動生成されたリンク
- フッターなどに埋め込まれ配布されたリンク
などが該当します。
無断で複製されたコンテンツ
無断で複製されたコンテンツとは、無断で第三者のサイトからテキストや画像をコピーすることで作られたコンテンツを指します。
また、他サイトから複製した文章を一部変更したとしても、サイト独自のコンテンツや提供できる価値が記載されていない場合は、ユーザーの役に立たないコンテンツのためSEOスパムと判断されます。
▼ 複製されたコンテンツに該当するのは以下になります。
・他のサイトのコンテンツをコピーし、(語句を類義語に置き換えたり自動化された手法を使用したりして)若干の修正を加えたうえで転載しているサイト
Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー:無断で複製されたコンテンツ
・ユーザーに対してなんらかの形で独自のメリットを提供することなく、他のサイトからのコンテンツ フィードをそのまま掲載しているサイト
・ユーザーに実質的な付加価値を提供することなく、他のサイトの動画、画像、その他のメディアなどのコンテンツを埋め込んだり編集したりしているだけのサイト
不正なリダイレクト
リダイレクトとは、サイトやページにアクセスしてきたユーザーを自動的に他のURLページに転送させる仕組みのことです。
不正なリダイレクトとは、検索エンジンにはAのコンテンツを読み込ませて、ユーザーはリダイレクトで別ページに飛ばしてBのコンテンツを見せたり、パソコンとモバイル端末とで、全く別のコンテンツを表示させたりするなどユーザーの本来のニーズに対応しない、リダイレクト設定を指します。
例えば、リダイレクトの正しい使い方として
- ホームページを移行したので、新しいサイトにリダイレクトをかける
- 複数に分けて展開していたページを一つに統合する際に、メインページにリダイレクトをかける
などであれば問題ないのですが、ユーザーと検索エンジンを欺くことを目的とした不正なリダイレクトは、SEOスパム行為とみなされる可能性があります。
スパム行為のある自動生成コンテンツ
スパム行為のある自動生成コンテンツとは、プログラムで自動的に生成されたコンテンツのことです。
殆どの場合、プログラムで生成されたコンテンツは他社サイトの文法を並べ替えただけだったり、ワードサラダで生成されたりと、ユーザーにとって価値の無いランキング操作を目的としただけのコンテンツとなります。
そのような低品質なコンテンツをサイトに掲載すると、当然スパムと判断されます。
▼ Googleの検索セントラルでは下記のようなコンテンツを自動生成コンテンツとみなしています。
・検索キーワードを含んでいるが、文章としては意味をなさないテキスト
スパム行為のある自動生成コンテンツ
・自動ツールで翻訳されたテキストが、人間によるチェックや編集を経ずに公開されたもの
・品質やユーザー エクスペリエンスを考慮せず、自動プロセスで生成されたテキスト
・類義語生成、言い換え、難読化などの自動化手法を使用して生成されたテキスト
・フィードや検索結果の無断複製によって生成されたテキスト
・複数のウェブページからのコンテンツを、十分な価値を加えることなくつなぎ合わせたり組み合わせたりしたもの
Chat GPTによって作成されたコンテンツが自動生成コンテンツに該当するか、意見が分かれていますが、SEM Plus編集部では、ユーザーにとって価値の高い内容であれば問題ないと考えています。
ただし、Chat GPTによって生成されたコンテンツを見ると、現状では品質の高い内容とは言えないことが殆どのため、SEM Plus編集部ではそのまま活用するのは難しいと判断しています。
その他のSEOスパム
さて、ここまで代表的なスパムSEO行為について解説してきました。
ここからはあまりメジャーではありませんが、注意をしておかないといけない、油断していると知らない間に行ってしまっているかもしれない、少しマニアックなSEOスパム行為を解説します。
誤解を招く機能
誤解を招く機能とは、検索エンジンがユーザーにとって利便性が高いサイトや、高品質なサイトを高く評価して検索順位を上昇させる仕組みを利用したスパムです。
具体的には、ユーザーや検索エンジンから評価される機能やコンテンツを作り、実際にはサイトで表記している機能やサービスを提供せずに、広告を見せたり別のサイトに誘導します。
例えば、
- 無料でPDFを統合することができる機能があると見せかけて、サイト内に呼び込み広告を見せる。
- アプリストアで使えるクレジットを付与すると記載して、実際には付与せず別のサイトに遷移させる。
などが該当します。
これらの行為はユーザーと検索エンジンを欺く行為となるため、SEOスパムに該当します。
【参考資料】
誤解を招く機能|Google 検索セントラル
内容の薄いアフィリエイトページ
内容の薄いアフィリエイトページとは、アフィリエイトを目的としたページを作成する際に、商品説明や料金・レビューなどを販売元のサイトや他のアフィリエイトページからコピーして転載した、独自性や付加価値のないページのことを指します。
本来のあるべきアフィリエイトページとは、アフィリエイターが実際に商品を使用し、自身の経験や体験を基にした評価を掲載するべきです。
第三者のサイトからコピーして持ってきた情報や、アフィリエイトリンクだけを掲載しているページを使ってユーザーに商品を勧める行為は、悪質SEOスパム行為と見なされます。
ユーザー生成スパム
ユーザー生成のスパムとは、サイト運営とは関係のない第三者が自身のサイトへのトラフィック獲得や被リンク獲得を目的に、他社のWEBサイトにコンテンツやリンクを設置する行為です。
例えば、ブログのコメント欄やフォーラムのスレッド(5ちゃんねるなどの特定の話題に特化した投稿ページ)に自身のサイトへのリンクを貼ることで、閲覧したユーザーを別サイトへ誘導しようとする行為などがおこなわれているサイトはスパムと判断されます。
これは、本来ユーザー同士の交流の場や意見交換をする場として使われるべき項目に、他の目的を持ったユーザーが参画することで、あるべき姿になっていないからです。
サイト運営者は、コメント欄を承認制にするなどの対応を予めしておきましょう。
機械生成トラフィック
機械生成トラフィックとは、検索結果のスクレイピングや自動生成したクエリをGoogleに送る行為を指します。これらの行為はGoogleが本来使用する必要の無いリソースを使うため、スパム行為とされています。
サイトのランキングを上げるスパム行為ではありませんが、サイトへのアクセスを増やすためにサジェストキーワードにサービス名や会社名を表示させる、サジェストSEO(虫眼鏡SEO)は自動生成したクエリに該当します。
サジェストSEOもガイドラインに該当するため、スパム業者から営業されても断るようにしましょう。
セキュリティの問題によるスパム
セキュリティの問題によるスパムは、サイト運営者が意図的におこなうスパムではなく第三者によって引き起こされるスパムです。
そのため、SEOスパムとは異なりますが、運営者がWEBサイトに対して万全のセキュリティ対策をおこなっていないことが原因で起きるため、注意喚起の意味も込めて紹介します。
ハッキングされたコンテンツ
ハッキングされたコンテンツとは、サイトを関係のない第三者に乗っ取られてしまい本来の所有者に許可なく、サイトに掲載されたコンテンツを指します。
悪質なハッカーは、ユーザーの個人情報を抜き取ろうとする「フィッシング攻撃」を目的にハッキングします。
ハッキングされた場合、ページに流入したユーザーが被害を受ける可能性があるため、Googleからスパムサイトと判断され検索結果に表示されなくなります。
また、別の目的としては、勝手にサイト内に隠しテキスト・隠しリンクを設置したり、クローキング設定を行ったりするなどして、GoogleからのSEO評価が下がるように手を加えます。
ハッキングはサイト運営者が意図して行えるような施策ではありませんが、セキュリティの脆弱性に付け込まれ、サイトをハッキングされるような事態に陥らないよう、普段からセキュリティには十分注意しましょう。
マルウェアや悪意のある動作
マルウェアとは、パソコンやモバイルデバイスで実行されるソフトウェアのうち、ユーザーに対して悪影響を与えることに特化して設計されたソフトウェアやアプリのことです。
マルウェアもハッキングと同様にサイト運営者ではなく、第三者によっておこなわれる行為です。そのため、検索順位を操作するSEOスパムとは属性が異なりますが、スパムと判断された場合は検索結果から削除されるため注意喚起も含めて紹介します。
ハッキングと同様、サイトのセキュリティを高めることで回避することができます。
Googleからスパムと判断されているかどうかの確認方法
GoogleからSEOスパム行為をしていると判断され、ペナルティを受けているかどうかは、サーチコンソールの「手動による対策」項目より確認することが出来ます。
ペナルティには監視員が目視で確認し、判断する「手動ペナルティ」とアルゴリズムが判断する「自動ペナルティ」があります。
手動ペナルティの疑いがある場合は、
- サーチコンソールにログイン
- セキュリティと手動による対策
- 手動による対策
にメッセージが来ていないか確認しましょう。
手動ペナルティを受けている場合、新着メッセージとして通知が来ています。

SEOスパムがペナルティになる理由
では、なぜGoogleはSEOスパムに対して厳しいペナルティを与えるのでしょうか?
答えは、Googleはユーザーの利便性と信頼性を高めて利用者を増やしていきたいからです。
Googleは、ユーザーに「良質かつ有益な情報を提供する」ことでユーザーからの信頼を得て検索エンジンのシェアを伸ばしてきました。検索結果に、SEOスパムをおこなっている低品質なサイトが表示されると、ユーザーからの信頼が低下し利用者が減ってしまいます。
例えば、SEOスパム行為の一つである「コピーコンテンツ」ですが、他サイトのコンテンツを丸々真似をしたコンテンツを評価していたのでは検索結果にはコピーコンテンツが氾濫し、ユーザーにとって有意義なオリジナリティのあるコンテンツが生まれなくなります。
ユーザーが検索した際に、同じような内容のWEBサイトしか出てこないのでは、ユーザーが再度Googleの検索エンジンを使用することはないでしょう。
Googleは、SERPs上の広告から利益を得ているため、Google検索エンジンの利用者が減少すると広告収入が減少しビジネスとして機能しなくなります。
このような状態になるのを避けるために、不正なスパム行為に関しては厳しいペナルティを与えているというわけです。
SEOスパムによってペナルティを受けるとどうなるのか
SEOスパムが原因によってペナルティが与えられたサイトは検索結果上での露出が大幅に制限されます。
具体的には、
- 当該のWEBサイト、もしくはWEBページの検索順位が下落、または検索結果に表示されなくなる
- 当該のWEBサイトがGoogleのインデックスから削除される
といった非常に厳しいペナルティを課せられます。
Google では、自動システムと、必要に応じて行われる人間による審査によって、ポリシーに違反しているコンテンツおよび動作の両方を検出しています。場合によっては、手動による対策を実施します。Google のポリシーに違反しているサイトは、検索結果での掲載順位が下がったり、まったく表示されなかったりすることがあります。
Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー
Googleからペナルティを受けると復旧までに膨大な時間がかかったり、不正行為の規模によっては復旧自体が困難になる場合があります。
SEOスパム行為は、検索結果に自身のサイトが表示されなくなる可能性のある非常にリスクのある取り組みということを覚えておきましょう。
SEOスパムにならないためにおこなうこと
SEOスパムとGoogleから判断されないようにするには、どのような行為をGoogleがスパムとみなすのか、事前に正しく理解しておく必要があります。
そのためには、本記事やGoogleのガイドラインを確認しておくことが大事です。
SEOスパムについて正しく理解することで、
- 意図しないスパム行為を防ぐ
- 第三者からおこなわれているSEOスパム行為を見つける
といったことができるようになります。
また、サイトを運営する基本的な考え方として「ユーザーにとって価値の高いサイトにする」を意識しましょう。
ユーザーではなく、検索順位を意識してサイトを運営すると、意図せずスパム行為をおこなってしまう場合があります。ユーザーファーストな考え方で運営していれば、SEOスパムになるような行為は自然としないでしょう。
SEOスパムと認定された際の対処法
万が一、GoogleからSEOスパムと判断され手動ペナルティを受けてしまった場合は、次の項目をチェック・対処しましょう。
- ペナルティの有無と内容の確認
- ペナルティになった要因をガイドラインから確認する
- サーチコンソールから再審査リクエストを送信する
■ STEP1. ペナルティの有無と内容の確認
サイト全体で検索順位が大きく低下した場合は、サーチコンソールの手動による対策に来ているメッセージを確認して、ペナルティの有無を確認しましょう。
ペナルティのメッセージが届いている場合はGoogleがどの項目に対してスパムと見なしているのか、確認してください。
■ STEP2. ペナルティになった要因をガイドラインから確認する
ペナルティの原因が分かったら、Google検索セントラルの「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」で挙げられているスパム行為一覧と照らし合わせ、具体的にWEBサイトのどういった部分や行為がペナルティの要因となったのかを確認します。
ペナルティになった要因を理解したら、対象箇所を修正します。
■ STEP3. サーチコンソールから再審査リクエストを送信する
スパムと判定を受けていると思われる箇所の修正作業が終わったら、サーチコンソール「手動による対策」の通知画面上に表示されている「審査をリクエスト」からサイトの再審査を申請しましょう。
- スパムと判定された内容の説明
- 修正するために取った施策、及びその手順
- 修正した結果
を、なるべく分かりやすく正確にまとめて報告するのがポイントです。
無事、審査が通れば手動ペナルティは解除されます。
SEOスパム まとめ
SEOスパムがどのような行為なのか正しく理解しておかないと、「知らず知らずの内にガイドラインに違反した施策をとってしまい、気付いたらペナルティを受けて、検索結果に表示されなくなってしまった」などという取り返しのつかないことになりかねません。
本項では、SEOスパムについて具体的な手法やペナルティを受けた際の対処法を解説しました。
是非、サイト運営の参考にしてください。
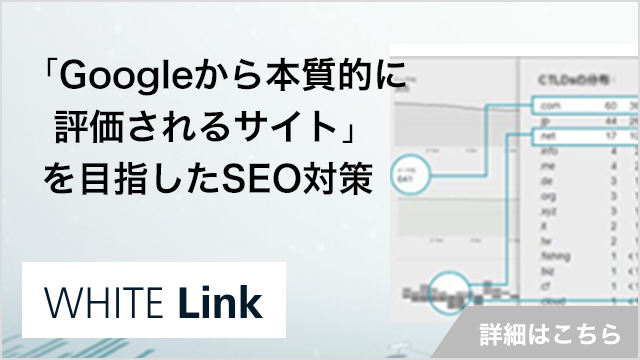
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














