サブドメインとは?メリット・デメリットと作り方を分かりやすく解説

今回は、複数のWEBサイトを運営する際に検討する事が多いサブドメインについて初心者向けに分かりやすく解説します。サブドメインを作成するメリット・デメリットや作り方、使用している企業の例、サブディレクトリとの違いを説明しています。サブドメインをうまく活用することでコスト削減やブランディングにも活用することができます。
サブドメインとは?
サブドメインとは、自社で取得した独自ドメインに任意の文字列を追加して作成されたドメインの事です。主要ドメインに、サブとして設定できるドメインという理由からサブドメインと呼ばれています。
サブドメインは、メインのドメインの先頭に「.」で区切られた文字列を追加します。例えば、example.comがドメイン名の場合、そのサブドメインはsub.example.comのようになります。

サブドメインは、主に1つの会社で異なる複数のブランドを展開している場合に使用されます。実際にサブドメインでWEBサイトを運用している企業の使用例を紹介します。
【楽天市場の例】
- メインドメイン:https://www.rakuten.co.jp/
- サブドメイン①:https://travel.rakuten.co.jp/(宿やホテルの予約サービスの楽天トラベル)
- サブドメイン②:https://tv.rakuten.co.jp/(日本国内向け動画配信サービスである楽天TV)
- サブドメイン③:https://books.rakuten.co.jp/(書籍やDVD、CDのオンライン書店の楽天ブックス)
このように、楽天の場合、独自ドメインは楽天市場のhttps://www.rakuten.co.jp/ですが、サービス毎にサブドメインで運用しています。
提供しているサービスごとに、サービスに関連する文字列を大元のドメインに足したサブドメインを使うことで、ユーザーはURLを見れば一目で楽天が運用するサービスということを理解することができます。
サブドメインのメリット
サブドメインのメリットは、ドメインの取得費用が掛からないことと、メインサイトのURLが含まれるためブランドイメージを維持してWEB集客が出来ることです。
また、メインサイトの効果を引き継ぐなどSEO面でも活用するメリットがあります。
新しくドメインを取得する必要が無いため費用を抑えられる
WEBサイトを複数運営するには、WEBサイトごとに独自ドメインを取得する必要があります。その場合、取得した独自ドメインに対してそれぞれ費用が発生するためサイトを増やす度に追加で費用がかかります。
例えば自社で5つのブランドを保有していて、それぞれ別ドメインを取得しようとすれば、5倍のコストと手間がかかります。
しかし、メインドメインがすでにあれば、その下にいくつでもサブドメインを無料で作成できるため、サブドメインを使うことでドメイン費用や管理の手間を抑えて複数のWEBサイトを運営することが出来ます。
ただし、設定可能なサブドメインの数の制限やサブドメインの追加には、別途オプション料金がかかるケースもあるので、契約中のサーバー会社へ確認が必要です。
ブランドイメージを維持してWEB集客ができる
製品やサービスごとに特化したWEBサイトを作成する場合、独自ドメインを取得するとそれぞれ一貫性の無いドメインを持つことになります。
ドメインに一貫性が無い場合、ユーザーは同じ企業が運用しているサイトだと認識するのに時間がかかるためブランドイメージを活用したプロモーションをする上で不利になります。
一方で、サブドメインを使うと、URLの中にメインサイトのURLが入るため、ユーザーは異なるサービスでも同一企業から提供されていると理解し安心します。
例えば、楽天の場合「rakuten.co.jp」が全ドメイン名に含まれることで、楽天の企業・ブランドイメージを維持しながら、異なる様々なサービスを提供しています。
メインサイトのSEO効果を引き継ぐことができる
新規でドメインを取得した場合は、ドメインのSEO評価は0からのスタートになりますが、サブドメインで作成した場合は、メインドメインの評価を一部引き継ぐことが出来るためSEO対策をおこなう上では有利になります。
ただし、メインサイトが「手動による対策ペナルティ」になっている場合やGoogleからマイナスの評価を受けている場合は、マイナスの評価も引き継ぐ可能性があります。
また、元々メインサイトが立ち上げたばかりの状態など、SEOで評価されていなければサブドメインで作成してもSEO効果はありません。
サブドメインのデメリット
サブドメインを使用するデメリットは、
- SSL証明書の発行に費用がかかること
- メインサイトを解約するとサブドメインのサイトも解約になること
- 検索結果に表示されない可能性がある
の3つです。
SSL証明書の発行に費用がかかる
サブドメインはドメイン取得費用がかかりませんが、SSL証明書はメインドメインとは別に取得したサブドメインの数だけ必要になります。
SSL証明書とは、WEBサイトとユーザー間の通信を暗号化することにより、データの安全性を保証する電子証明書です。GoogleはSSL証明書を発行したセキュリティ面で安全なhttpsのWEBサイトを評価する仕組みのため、WEBサイトから集客をおこなう上でSSL証明書の発行は必須となります。
SSL証明書の発行はサイトごとに取得する必要があるため、サブドメインで作成したWEBサイトの分だけ費用がかかります。
メインサイトを解約するとサブドメインも解約になる
一般的にメインサイトを解約する場合、そのメインサイトに関連するサブドメインが自動的に解約になります。
メインサイトのドメイン名をベースにしているサブドメインは、メインサイトと一緒に管理されていることが多いため、メインサイトを解約するとサブドメインもアクセスできなくなる可能性があります。
ただし、メインドメインとは別にサブドメインに独自の契約や設定がある場合は、サブドメインが独立して管理されている可能性があるため、メインサイトの解約が直接影響するとは限りません。
メインサイトを解約する前に、契約しているサービスプロバイダーに確認してみましょう。
検索結果に表示されない可能性がある
Googleは、2013年にダイバーシティアップデートを行い検索結果に同一ドメインを2つ以上表示させないようにしています。(指名検索などキーワードによっては表示されます)
サブドメインもメインドメインと同じドメインとしてカウントされるため、サイト内で扱っているテーマやキーワードが重複している場合は、どちらか片方のドメインが検索結果に表示されない可能性があります。
サブドメインでWEBサイトを作成する場合は、メインドメインのテーマと異なる場合に作成するようにしましょう。
サブドメインの作り方
サブドメインの作成方法は、メインドメインを設置しているサーバー会社によって異なります。そのため、まずはサーバー会社がサブドメインの取得に対応しているかどうかを確認します。
契約しているサーバー会社がサブドメインに対応している場合は、管理画面内に「サブドメインの設定」に関する項目があるためそこからサブドメインを追加していきます。
以下のリンクから、各サーバー会社のサブドメインの設定方法に関するガイドを参照の上進めてください。
- エックスサーバー:https://www.xserver.ne.jp/manual/man_domain_subdomain_setting.php
- ロリポップ:https://lolipop.jp/manual/user/doku-subsett/
- サクラインターネット:https://help.sakura.ad.jp/domain/2148/
- お名前ドットコム:https://www.onamae-server.com/guide/rs/p/9
※ 上記以外のサーバー会社と契約している場合は、Googleで「サブドメイン 作り方 サーバー会社名」で検索すると、作成ガイドが検索結果に表示されます。
サーバー会社によって異なりますが、サブドメインを作成してから反映されるまでには数時間~数日かかります。数日待ってもDNSの情報が反映されない場合は、サーバー会社に問合せてみましょう。
【サブドメイン名の決め方】
サブドメイン名は好きなように作成出来ますが、WEBサイトのテーマやサービス名に合わせて作成するのがオススメです。
サブドメインを活用している企業の例
サブドメインを効果的に活用している多くの企業を紹介します。
紹介する企業はサブドメインを使用して、さまざまな製品、サービス、キャンペーンサイト、採用サイトなどを区別し、ユーザーに対して一貫したブランドイメージを維持しながら目的に応じた情報提供を行っています。
サブドメイン名にするかどうかの参考になるため、いくつか紹介します。
Google自体もサブドメインを活用しています。Googleは様々なサービスを提供していることで知られていますが、検索エンジン・ニュース・翻訳・ストアなど各サービスごとにサブドメインを使用しています。
■ Googleニュース

■Googleストア

■ Google翻訳

Yahoo! JAPAN
サブドメインで代表的な企業といえばYahoo!が上げられます。Yahoo!は古くからYahoo!ニュースやYahoo!天気、Yahoo!オークションなどサービスごとにサブドメインを活用しています。
■ Yahoo!検索

■ Yahoo!ニュース

■ Yahoo!天気・災害

コクヨ株式会社
文具や家具で有名なコクヨ株式会社は、コーポレートサイトのサブドメインで採用サイトを作っています。
採用サイトをあえてメインサイト内に作らないことで、採用に力を入れていることをユーザーに分かりやすく伝えています。
■ 採用サイト

■ コーポレートサイト

厚生労働省
国の公的機関である厚生労働省もサブドメインを活用しています。厚生労働省は、取り組んでいる事業ごとにWEBサイトを分けてサブドメインで運用しています。
URLにメインドメインのURLが含まれているため、ユーザーは安心してサイトを利用することが出来ます。
■ 厚生労働省

■ 治療と仕事の両立支援ナビ

■ こころの耳:働く人のメンタルヘルス

サブドメインとサブディレクトリとの違い
サブドメインがメインドメインの前に「.」を付けた独立したドメインなのに対して、サブディレクトリは、メインドメインのURLの後ろに「/」を付けたサイト内にある1つのページです。
サブドメインは検索エンジンからはメインサイトとは独立したWEBサイトと判断されますが、サブディレクトリは1つのドメインの後ろに「/」を付けて階層を作り、下層ページとして運用するため、検索エンジンからは全てメインサイト内のページとして見られます。
【URLの違い】
- メインのドメイン:example.com
- サブドメイン:sub.example.com
- サブディレクトリ:example.com/sub
また、サブドメインとサブディレクトリではメインサイトに与えるSEOの影響にも違いがあります。
サブドメインは独立したドメインになるため、サブドメイン内のコンテンツ品質を高めてもメインドメインのSEO効果には影響はなく、あくまでサブドメインで運用しているWEBサイトの評価が高くなります。
一方、サブディレクトリはメインドメイン内にあるURLのため、コンテンツの品質を高めたり、関連するページを増やす事でGoogleからメインドメインの評価が高くなります。
まとめ
WEBサイトを複数する際は、サブドメインでの運用を行うことでコストを下げて運用することが出来ます。
また、サブドメインはURLにメインサイトのURLが含まれています。そのため、メインサイトとは別のテーマのWEBサイトを作成する場合は、メインサイトのブランド力をユーザーに伝えるためにもサブドメインを活用しましょう。
尚、サブドメインとサブディレクトリどちらで運用する方がお悩みの場合は、是非弊社までご相談ください。ビジネスモデルやSEOの観点から最適なご提案をさせて頂きます。
以上、サブドメインについてでした。
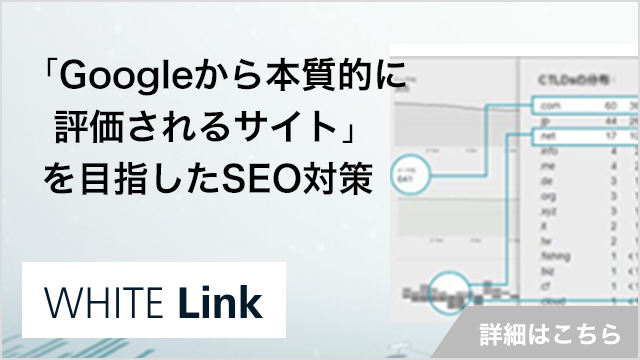
RECOMMENDED ARTICLES
ぜひ、読んで欲しい記事














